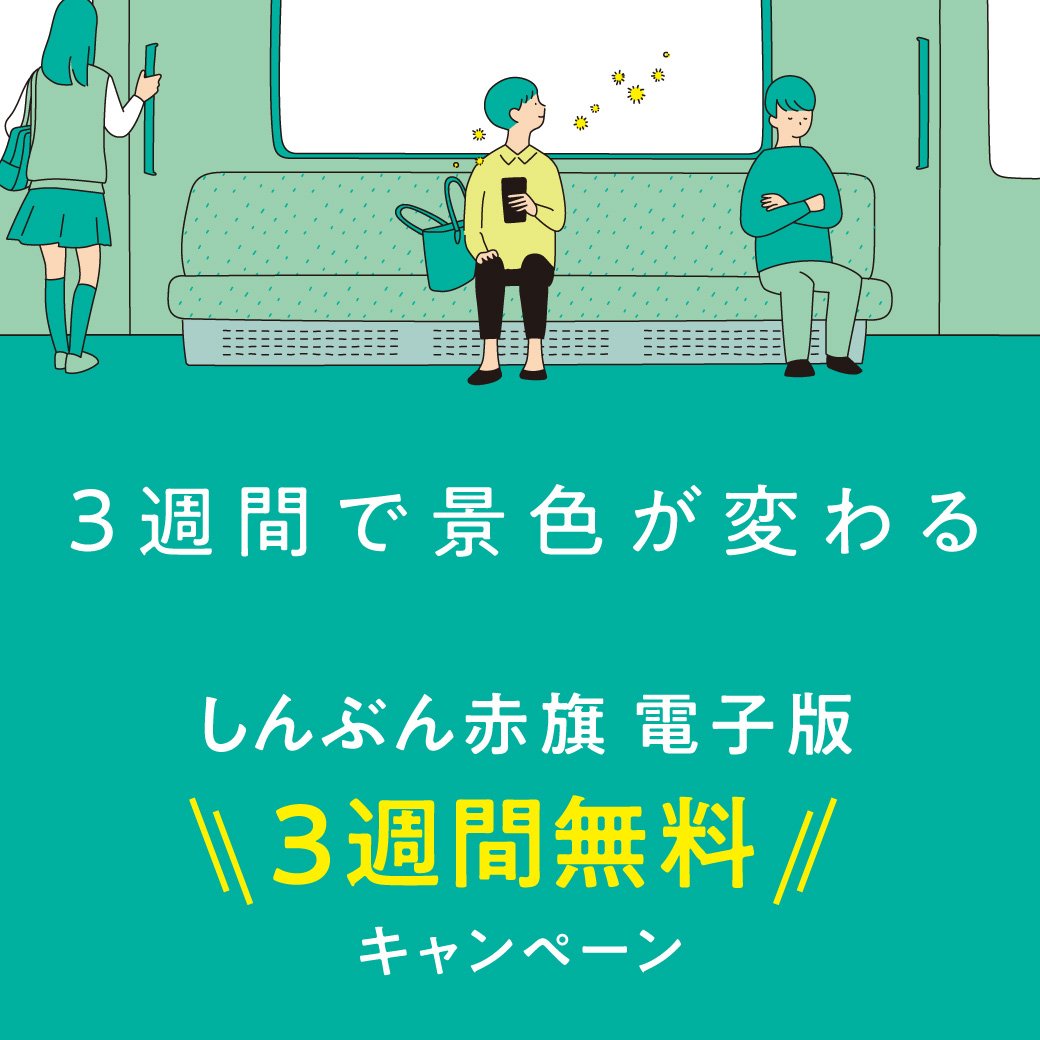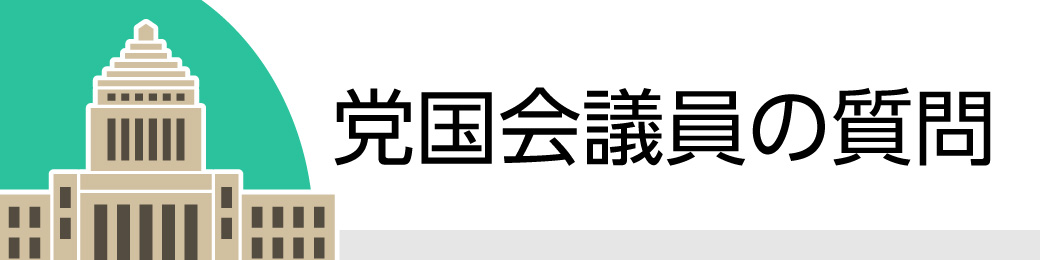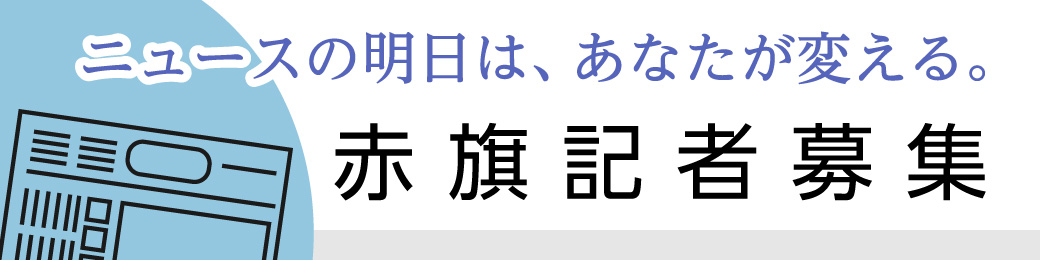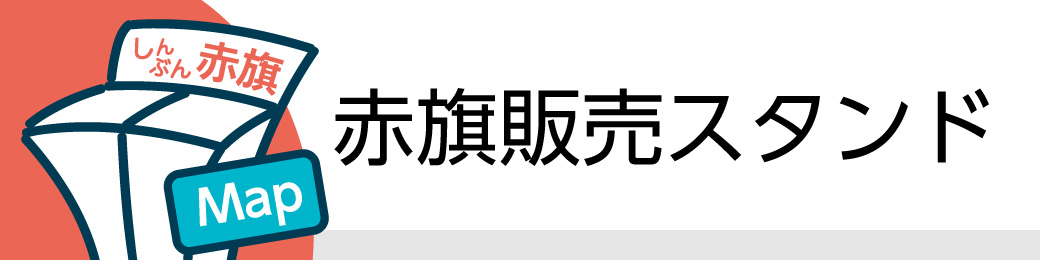2025年4月7日(月)
きょうの潮流
春の訪れとともに、咲きこぼれる桜花。東京の桜の標本木がある靖国神社には、家族連れやカップル、外国人観光客をはじめ、たくさんの姿がありました▼ソメイヨシノやヤマザクラなど境内にある数百本の桜が迎え、めでる人びとの顔も自然とほころびます。〈春ごとに花のさかりはありなめどあひ見むことはいのちなりけり〉。「古今和歌集」にもあるように古来、桜は生命の輝きの象徴としてたたえられてきました(『桜と日本人』)▼そこに死の影をまとわせたのは武士や軍人の死生観でした。主君やお国のために潔く命をささげる。散りゆく自身の命を桜にたとえ、死の花、軍国の花、そして靖国の花として▼「歩兵の本領」や「同期の桜」といった軍歌にも使われ、「散華(さんげ)」のことばのもとで、あまたの若者が死に追いやられていきました。「英霊」が再会する場所としてあがめられてきた靖国には、戦友会や同期会、戦没者の遺族から献木された桜も多い▼「武人の華とも謂(い)ふべき染井吉野桜をこの地に植樹す。春爛漫(らんまん)の桜花に想ひを馳(は)せ、“二魂一命”の夢叶(かな)い、再会の喜びを共にし、その盟約を果たす所以(ゆえん)なり」。「海軍十三年桜」には献木の由来がそう記されていました▼各地でにぎわうお花見。大切な人といのちの息吹をことほぐ様子は、死の影とはほど遠い。戦死を美しく飾り、いまだに侵略戦争を正当化する靖国神社のゆがんだ桜観からも。いまあるのは、死の花の呪縛から解き放たれ、美しい花を慈しむ人びとの姿です。