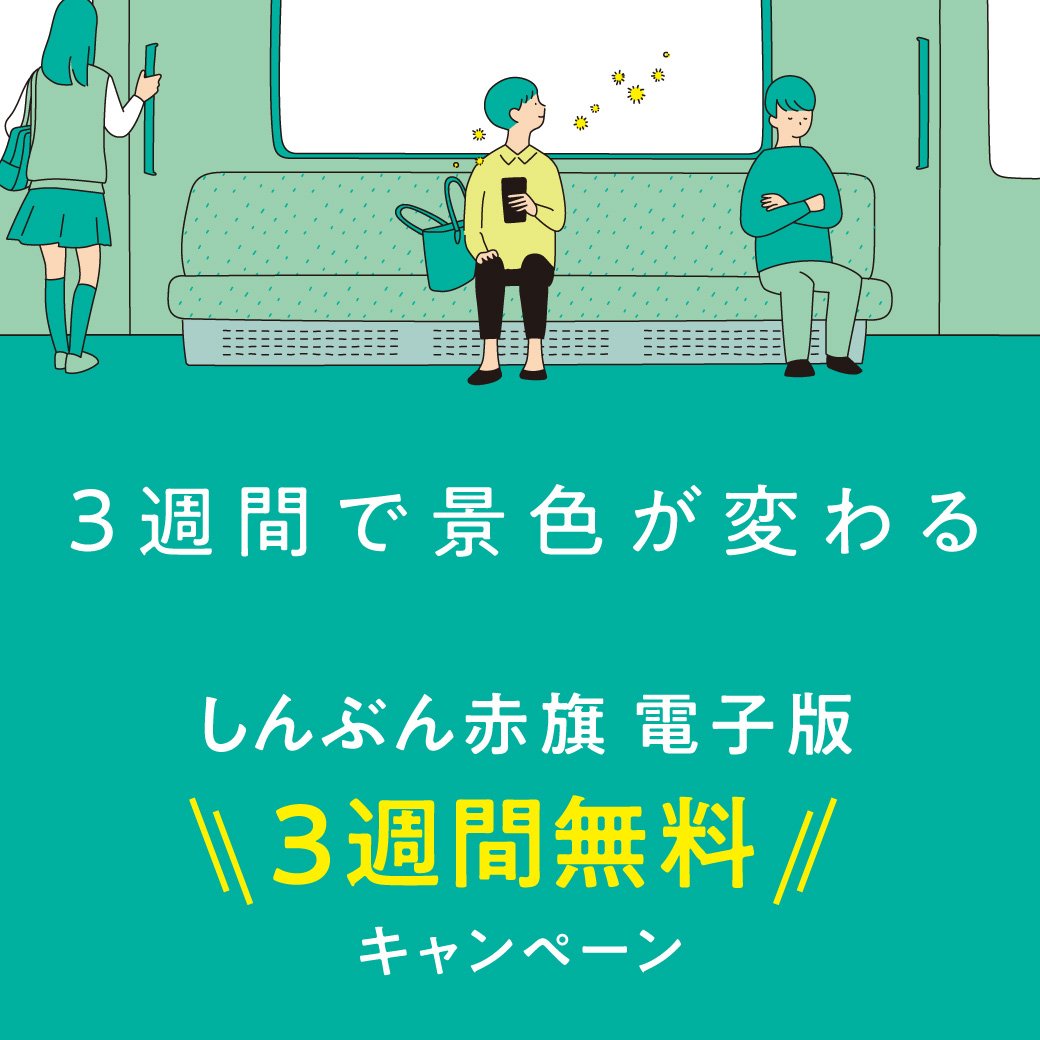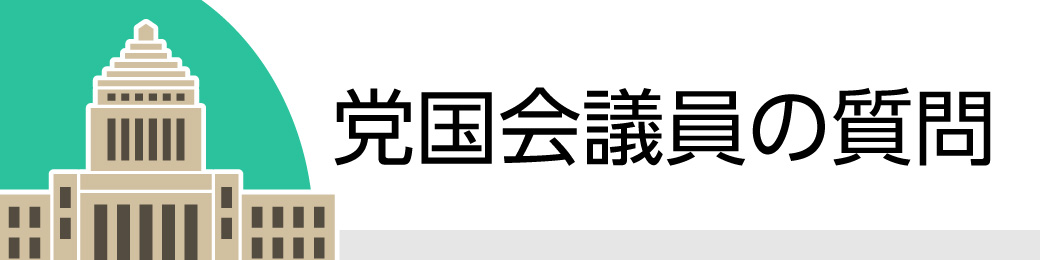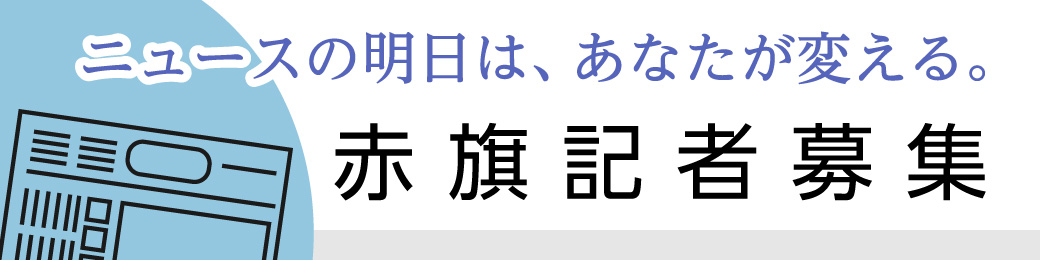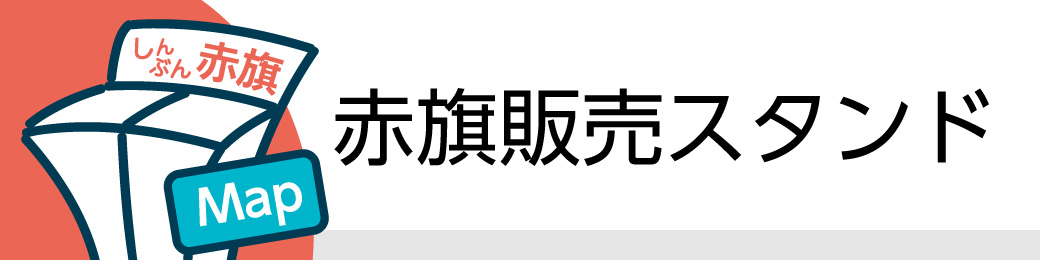2024年12月27日(金)
主張
温暖化対策計画
低すぎる削減目標の見直しを
温暖化による極端な異常気象が頻発しています。このままでは南極氷床の融解など不可逆的な事態を招き、島の水没や食糧危機など人類の存続に関わる問題が生じます。
これを避けるには、産業革命前からの気温上昇を1・5度以内に抑えるよう、世界全体で温室効果ガス(GHG)の排出を2013年比で35年に66%削減することが必要です。先進国であり、世界第5位の排出大国である日本はさらなる削減が求められています。
しかし、環境省と経済産業省合同の審議会は24日、35年の削減目標を60%とする地球温暖化対策計画案を示しました。日本共産党は目標を75~80%とするよう申し入れを行いました。
■批判の声を「黙殺」
審議会では、「1・5度目標を守る水準を下回っており国際的に説明できない」「削減のためのコストばかりが議論され、被害やその対策のためのコストが考慮されていない」と異論が噴出し、日程を延長する異例の事態となりました。
会議では、目標引き上げを求める委員の意見書の読み上げが拒否されるなど「黙殺」され、経団連の提言と酷似した60%案が唐突に提案されました。「シナリオありきだ」と批判があがり、若者たちは目標引き上げと審議の透明性を求め緊急署名を提出しました。
世界では再生可能エネルギーが最も安い電源となり、燃料高の中、エネルギー安全保障上からも加速度的に導入が進んでいます。石炭産出国の豪州やインドネシアも石炭火力の廃止を決め、再エネの大量導入に動いています。
日本は化石燃料を輸入に頼っており、再エネ推進の経済効果は世界的にみても大きく、太陽光発電の屋根置きや遊休農地の一部活用だけでも大規模導入が可能だと指摘されます。しかし政府の計画には、再エネ導入などGHG排出削減の具体的な対策がなく、会議で批判の声があがりました。
リコーなどの企業が参加する「日本気候リーダーズ・パートナーシップ」は「再エネ調達は企業にとって喫緊の課題」「日本の競争力が脅かされかねない」と、35年までに再エネ比率を60%以上とし、75%のGHG削減を求めました。
■背景に巨額の献金
日本では原発と、火力発電存続のためのアンモニア混焼などの新技術の開発に巨額な支援が行われ、再エネ導入は停滞しています。この遅れを逆手にとって、会議では経団連の代表が、60%目標をさらに引き下げるよう要求しました。
さらに、政府はこの新技術をアジアなどで普及し石炭火力の延命を図っており世界の脱化石燃料を遅らせるものとなっています。
この日本の政策の背景には、今後衰退が予想され、政府の支援が必要な火力や原発関連企業から自民党に巨額の献金が行われ、経団連を通じて彼らが要求する政策を政府が実行している実態があります。
欧州などでは大電力の火力発電から、地域住民主体の再エネへ「システムチェンジ」が進められ、地域の活性化につながっています。日本でもこれを進めるとともに、一部の企業の利益のために政策がゆがめられる今の政治の「システムチェンジ」が求められます。