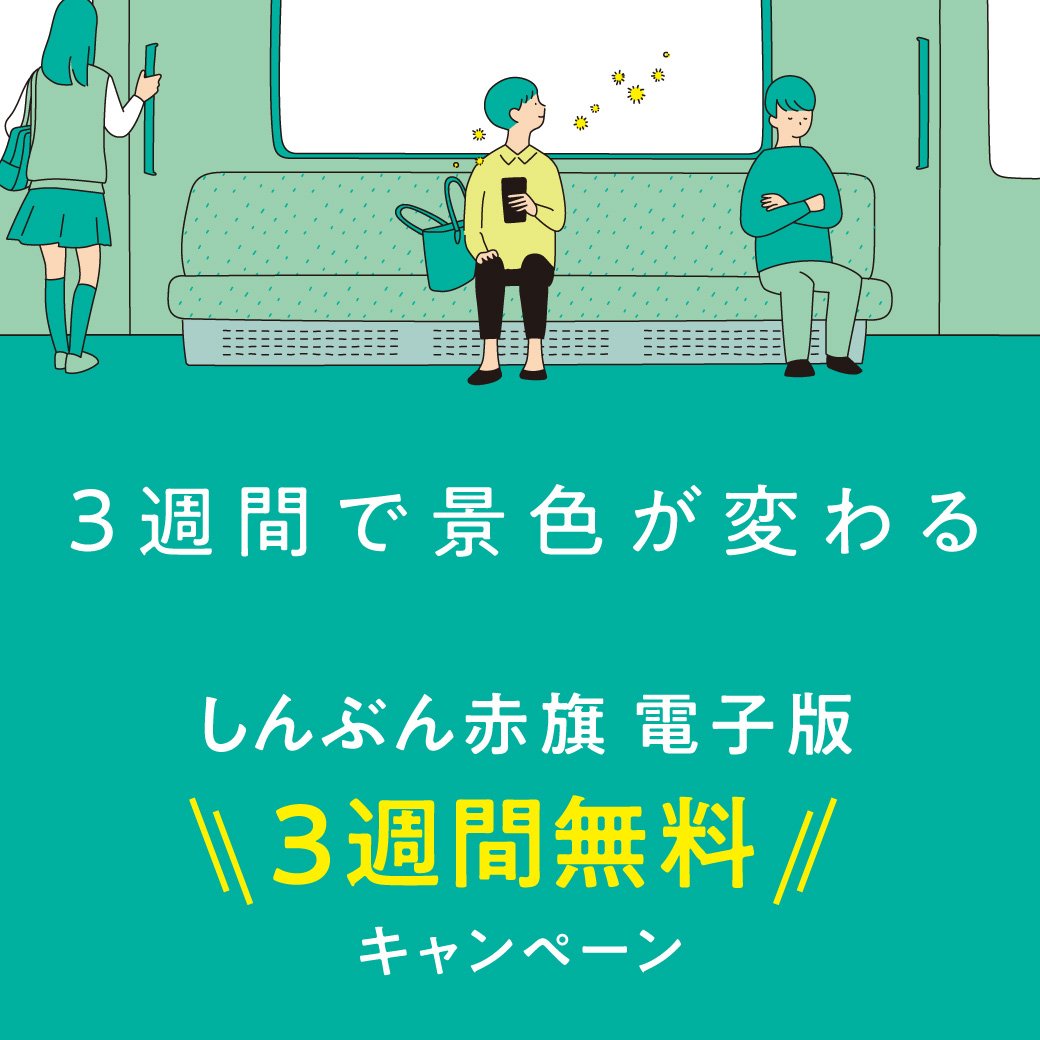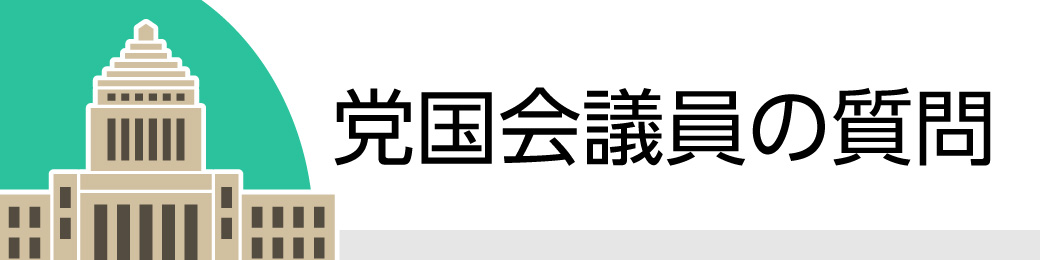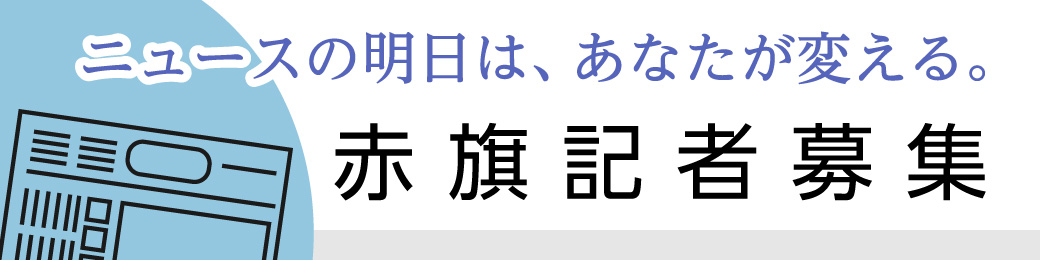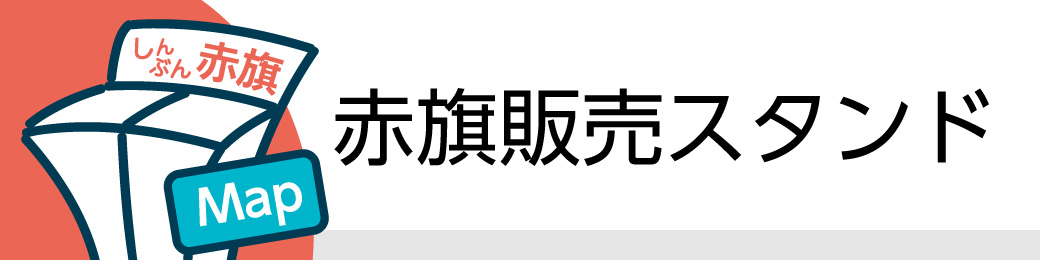2024年1月8日(月)
避難生活 環境劣悪
硬い床で就寝 今日もパン1個
教訓いかし命守る手立てを
能登・被災地
「段ボールを敷いて硬い床で寝ている」「昨日も菓子パン1個、今日もパン1個だ」―。1日に発生した能登半島地震の被災地で、2016年の熊本地震の避難所で見たのと同じ光景が繰り返されています。7日になってようやく風呂に入れた人。排せつ物を袋にためて家に“保管する”人。車中泊の車が列をなす駐車場―。避難生活の衛生環境は最悪です。(桑野白馬)
 (写真)津波の被災者たちが避難する松波中学校の体育館=5日、石川県能登町(細野晴規撮影) |
熊本地震や11年の東日本大震災で、痛ましい災害関連死が起きました。避難所に段ボールベッドを導入するなど、安価で被災者の健康を最低限守る知見もこの間、積み上げられてきました。これらが生かされていないのは、どういうことなのでしょうか。
昨年5月には石川県珠洲市で震度6強の地震がありました。「いつ大災害が起こってもおかしくない状態だった。それでも抜本的対策が取られていないのであれば、見捨てられた気分だ」と憤る人もいます。
石川県では、大規模災害に対する備えが明らかに不足していました。“油断”を生んだ一因は、県の地域防災計画です。地震被害の想定を見ると、「災害度は低い」と書かれており、26年前から更新されていません。
同計画には「県下の断層の分布状況と活動度との関係は十分に解明されていない」とも明記されています。志賀町にある北陸電力志賀原発周辺の断層が連動して動けば、大事故が起こる可能性もあります。
志賀原発がありながら、なぜこれほど甘い想定なのか。原発ありきの政策が影を落としてはいないでしょうか。
いま、自治体職員は自身も被災していながら避難者の生活を懸命に支えています。しかし、職員の使命感頼みでは限界があります。
日本共産党の佐藤正幸県議は「自治体職員が削減されてきた結果、マンパワーが足りていない」と指摘します。
石川県は1999年には41市町村ありました。それが合併の末、現在は19市町になりました。広域合併や民間委託、人員削減が防災に弱い地域を生み出しています。そのしわ寄せを最後に受けるのは地域の住民です。住民の声に寄り添い、命を守るための防災対策をいま一度、考え直す時です。