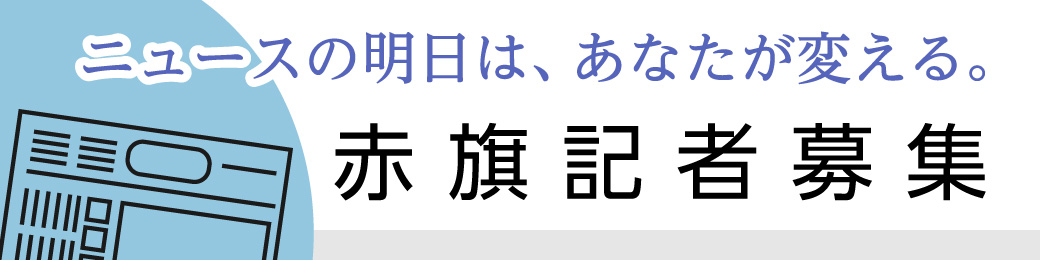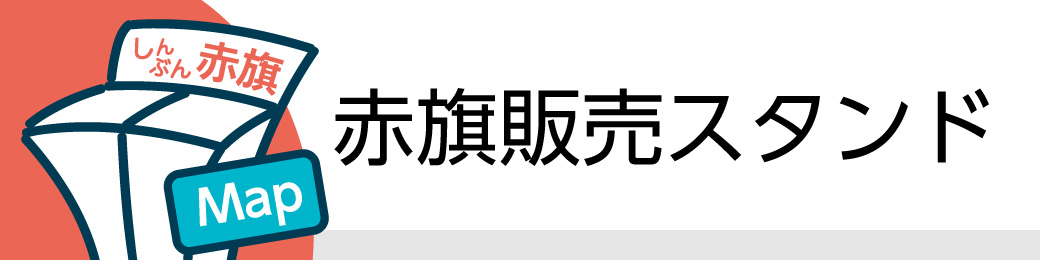私たちは、毎日、新聞やテレビなどメディアが流す膨大な情報のもとで生活しています。それではいま日本のメディアは健全な状態にあるといえるでしょうか。わけても巨大メディアが日本と世界の真実の姿を公正に伝え、また「権力のチェック役」という仕事を果たしているといえるでしょうか。今日の日本の巨大メディアの問題点を、さまざまな角度から考えてみたいと思います。
日本の巨大メディアの社会的影響力―19世紀のイギリスと比較して
まずお話ししたいのは、現代日本の巨大メディアの社会的影響力の大きさについてです。それを二つの角度から見てみたいと思います。
一つは、歴史的に見て、社会にたいするメディアの影響力がどれだけ大きくなっているかという問題です。私たちの大先輩であるマルクス、エンゲルスが活躍した19世紀のヨーロッパと比較するとどうなるでしょうか。
当時、資本主義が一番発達していたイギリスのメディアがどれだけの影響力をもっていたかを調べてみました。日刊紙で最大の発行部数をもっていたのはタイムズ紙ですが、部数は5万5000部にすぎません。当時のイギリスの人口は約2000万人ですから、人口比ではわずか0・3%程度の部数ですが、それでも「時の政界の指導者や、政府の更迭まで、その意思のままであるとする絶大の力」を、タイムズ紙はもっていたといいます(『イギリス新聞史』、ジャパンタイムズ、1984年)。
21世紀の日本はどうなっているでしょう。日本の日刊新聞の部数は、合計で約5100万部といわれています。そのうち、5つの大手全国新聞の合計で約2600万部です。
日本の人口の半数近い部数が発行されているわけですが、そこに19世紀にはなかった新たな媒体もくわわります。テレビとラジオです。さらに、インターネットのような、使い方によっては国民の運動にもプラスになるようなものもありますが、テレビとラジオなどの放送メディアの影響力も甚大なものとなっています。
19世紀のイギリスでは、政治・思想・文化の分野でのたたかいの舞台は、5万5000部のタイムズ紙という規模だったのが、現代の日本では約5100万部の日刊新聞、それにテレビ、ラジオがくわわって圧倒的な政治・思想・文化への影響力をもっている。たたかいの舞台がこれだけ巨大化しているのです。
大手新聞とテレビ局が系列化―欧米にはない「クロスオーナーシップ」
いま一つ、別の角度で現代日本の巨大メディアの現状を見てみたいと思います。それは、現代の世界の他の国ぐにと比べてどうかという問題です。
まず新聞ですが、日刊紙で約5100万部という発行部数は、先進国を対象にしたOECD(経済協力開発機構)の調査によると、絶対数で見ても世界一なのです。第2位のアメリカの4900万部、第3位のドイツの2000万部と比較しても、たいへんな数だということを痛感します。
日刊新聞の読者率(成人人口比)はどうでしょうか。世界新聞協会(WAN)や各国資料からOECDが取りまとめた調査によると、これも日本は92%で主要国で断然トップです。カナダが73%、ドイツが71%、アメリカが45%、イタリアが45%、フランスが44%、インドが37%、韓国が37%、メキシコが34%、イギリスが33%、トルコが31%、ロシアが11%となっています。日本は世界で最もよく新聞が読まれている国なのです。
もう一つ重要な問題は、テレビです。日本のテレビには、ある異常な特徴があります。それは、読売新聞は日本テレビ、産経新聞はフジテレビ、朝日新聞はテレビ朝日、毎日新聞はTBS、日経新聞はテレビ東京というように、大手新聞社とテレビ局が完全に系列化されているということです。かなりの資本を新聞社がもっていて、株主として支配力を発揮している。大手新聞とテレビは、こういう関係にあるのです。これを「異業種メディアの所有」(クロスオーナーシップ)といいます。放送メディアと新聞メディアという異なるメディアを、単一の営利企業が独占するというやり方です。日本ではこれが大手新聞と全国ネットのテレビとの間で、全国的規模でおこなわれています。
実は、このような「クロスオーナーシップ」は、欧米の先進国では見られないものなのです。なぜかというと、放送メディアと新聞メディアは、互いにチェックしあう必要があると考えられているからです。放送メディアが暴走したら、新聞メディアが抑える。新聞メディアが暴走したら、放送メディアが抑える。お互いにチェックすることが必要だと考えられています。「クロスオーナーシップ」では、そうした言論の相互監視、相互チェック機能、言論の多様性が失われる危険がある。
ところが日本では、「クロスオーナーシップ」が極端な形でおこなわれ、5つの大手全国新聞とその系列のテレビ局が同じ方向の内容の報道を、相互チェックもなく流し、国民の意識に圧倒的な影響を与えている。
これが日本の巨大メディアの現状です。世界で一番新聞がたくさん発行され、全国的規模で大手新聞社が「クロスオーナーシップ」で系列のテレビ局に支配権をもつ。こういうがんじがらめの巨大メディアの構造ができあがっている国というのは、欧米の先進国には他に見られない異常なものなのです。
ニューヨーク・タイムズ紙―「輪転機を十四階にあげても戦い抜く」
そういう形で、国民世論に圧倒的な影響力をもつ日本の巨大メディアが、「権力のチェック役」というメディア本来の仕事を果たしているでしょうか。率直にいってそれを放棄してしまっている。「チェック役」どころか、「権力と一体化」して、古い体制の「守護神」のようになっている。ここにたいへん深刻な問題があります。
私は、ここで日本の巨大メディアを、欧米のメディアと比較してみたいと思います。もちろん、欧米諸国のメディアも時の支配勢力の影響や制約を受けています。そこにはいろいろな問題点があります。ただ、そういう影響や制約を受けつつも、「権力のチェック役」としての役割をさまざまな形で果たしてきていることも事実です。
たとえばアメリカのメディアはどうでしょう。もちろん、アメリカのメディアにもいろいろな問題点があります。しかし、時の政府の不正に正面から立ち向かい、ジャーナリズムの歴史に残る「二つの頂点」といわれる記録を残しています。
その一つは、1971年にニューヨーク・タイムズ紙が、ベトナムの「トンキン湾事件」(1964年)は、アメリカ軍部のねつ造だったことを示すアメリカ国防総省の秘密報告書―「ペンタゴン・ペーパーズ」を暴露したことです。「トンキン湾事件」というのは、「北ベトナムのトンキン湾で、米駆逐艦が北ベトナムの魚雷艇から攻撃を受けた」というねつ造を当時のジョンソン政権がでっちあげ、それを口実に、北ベトナム攻撃(北爆)を開始し、ベトナム侵略戦争の全面化につながった謀略でした。これがねつ造だったことを、ニューヨーク・タイムズ紙が暴露していくのです。ニューヨーク・タイムズ紙は、この報道によって、ジャーナリズムの最高の名誉とされるピュリッツアー賞を受賞しました。
この時のニューヨーク・タイムズの「覚悟」を示す資料として、私が印象深く読んだのは、『メディアの興亡』(杉山隆男著、1986年、文藝春秋)です。「ペンタゴン・ペーパーズ」は、米国防総省元職員のエルズバーグ氏が持ち出し、ニューヨーク・タイムズ紙のニール・シーハン記者に渡しました。このシーハン記者に、小谷正一氏(毎日新聞退職後、電通顧問などをつとめる)が質問しているやりとりの場面があるのです。その部分を引用させていただきます。
「……小谷はゆっくりと言葉をついだ。
『シーハンさん、あなたが書いた記事は一つの政府を倒すぐらいの力を持っている。いわば権力と対決する記事だ。いくら世界に冠たるニューヨーク・タイムズといえども、そうした重大な、ことによったら会社を危機に引きずりこむかもしれない記事をのせようという時は、やはり会議にかけるんでしょうね』
『いや、会議なんて、そんな大げさなものはありません』
シーハンは笑って答えた。
『あの時は、ぼくが副社長のジェームズ・レストンに呼ばれて、ザルズバーガー社長もいるところで例の秘密文書について話を聞かれただけです』
『レストンはどう言ったのですか』
『ひと言、これは本物か。ぼくが、本物です、と言ったら、レストンは、わかった、と言ってGOサインを出しました。そのあとでレストンは部長会を開いて一席ぶちました。これからタイムズは政府と戦う。かなりの圧力が予想される。財政的にもピンチになるかもしれない。しかし、そうなったら輪転機を二階にあげて社屋の一階を売りに出す。それでも金が足りなければ今度は輪転機を三階にあげて二階を売る。まだ金が必要というなら社屋の各階を売りに出していく。そして最後、最上階の十四階にまで輪転機をあげるような事態になっても、それでもタイムズは戦う……』
小谷はシーハンの話を聞きながら、日本の新聞社とアメリカの新聞社はこうも違うものなのかと愕然とした。タイムズは社屋の一階一階を売りに出し、それこそ身を削りながらもなお言論の自由を守り抜くために政府と戦うという。ところが日本はどうだ。社屋を売って政府と戦うどころか、社屋をたてるために政府から土地を分けてもらっている。読売は大蔵省が持っていた土地に新社屋をたてたばかりだし、毎日の敷地のうち竹橋寄りの部分は皇宮警察の寮、つまりは国有地だったところだ。日経もサンケイも社屋がたっているところは、もとはと言えば大蔵省の土地である。そして朝日だって築地の海上保安庁の跡地に社屋をつくろうとしている。日本の大新聞という大新聞がすべて政府から土地の払い下げを受けて『言論の砦』をたてているのだ。これで政府相手にケンカをやろうというのが、どだい無理な話なのである」
最上階の十四階まで輪転機をあげる事態になっても、戦い抜く。それこそ社運をかけて権力に立ち向かうわけです。ジャーナリズムの気骨を感じますね。それに比べて、日本の大新聞は情けないと、愕然とした思いで聞いた。たいへんに生々しいやりとりです。
ウォーターゲート事件―大統領を辞任に追い込む徹底した追及
いま一つは、1972年におきたウォーターゲート事件の報道です。ワシントンのウォーターゲート・ビルの民主党本部を、ニクソン(当時のアメリカ大統領)陣営が盗聴をしていたという事件です。
これを暴露・追及していったのは、ワシントン・ポスト紙でした。「ポスト」は、政権からの強い反発や圧力を浴びながら孤軍奮闘し、徹底した調査報道で事件を追及していきます。事件が大がかりな選挙妨害事件の一部であり、資金はニクソン再選委員会から出て大統領補佐官と前司法長官が管理していたことなど、事件と再選委員会の関係、そしてニクソン大統領とその側近の策謀であることを明らかにしていきます。
ニューヨーク・タイムズ紙やロサンゼルス・タイムズ紙も報道に参加し、連邦議会が調査をはじめ、下院の司法委員会が史上初の大統領弾劾決議を採択し、ニクソン大統領を辞任に追い込んでいきました。時の大統領を辞任に追い込むまで徹底した追及をやりぬいた。ワシントン・ポスト紙は、社運をかけて戦い抜いたわけです。
すでにのべたように、アメリカのメディアにはいろいろな問題点があります。イラク戦争開戦時には、主要メディアがこぞって戦争を支持し、全体としては戦争をあおる役割を果たしました。
ただ、イラク戦争をめぐっても、その後の報道においては、独自の調査も駆使して、イラクのアブグレイブ刑務所に収容されているイラク人に対して米兵が虐待をおこなっている写真を放映したり、米国人傭兵を殺害して歓喜する群衆を報じるなど、政府や軍を揺るがし、「正義の戦争」と信じる米国民に衝撃を与え、その後の撤退を求める世論の拡大に大きな影響を与えました。さらに、ニューヨーク・タイムズ紙、ワシントン・ポスト紙などの主要メディアは、イラク開戦にかかわるみずからの報道を検証する記事を掲載し、誤りを認めました。誤りに対しても、なかなか潔いところがあるのです。
イギリスのBBC―イラク戦争で英政府による情報のねつ造を報道
イギリスはどうか。イギリスのメディアで記憶に新しいのは、イラク戦争の報道、時のブレア政権と真っ向から対立したBBCの報道です。
BBCといえば、日本のNHKにあたる放送局です。そういう放送局が、イラク開戦後、ブレア首相が〝イラクは45分以内に大量破壊兵器を実戦配備できる態勢にある〟という報告書をねつ造したと報道するのです。BBCの報道は、「英政府は、情報部の意向に反し、イラクの大量破壊兵器について誇張する表現を書き加えた。それは首相官邸の指示である。また官邸はそれが間違いであると知っていて行った」というものでした。
これにたいして、ブレア首相は、BBCに抗議して、訂正を求めますが、BBCの当時の会長グレッグ・ダイク氏は、これを突っぱねます。議会がこの問題での調査委員会を設置するまでに事態は発展します。議会が設置したハットン委員会は、政府の情報操作について指摘しつつも、「45分問題」を不問に付し、BBCの落ち度のみを攻撃する報告書を発表し、ダイク会長は辞任します。これにたいして、数千人のBBC職員が全国で街頭デモをおこない、デーリー・テレグラフ紙の1ページを買って、ダイク前会長支持、BBCの独立性を守れとの全面広告をのせます。
グレッグ・ダイク元会長は、回想録で次のようにのべています。
「BBCの会長としての私の役割は、イラク戦争に対する私の個人的な感情とは別のものだった。戦争に発展していく過程での出来事と、戦争そのものを、できるだけ公正に伝えていくことが、われわれの仕事であった。政府の宣伝機関になることがBBCの仕事ではないというのは当然のことであったし、また戦争に反対している人たちの意見を誇張して伝えるというのも、われわれの仕事ではなかった。われわれの仕事は、誰の肩も持つことなく、ニュースをできるだけ公正に伝えるというものだった」
「民主主義社会では、メディアと政府とは決定的に違う役割を担っており、放送メディアが中心に持つ役割の一つが、時の政府に対して疑問を投げかけ、彼らがかけてくるいかなる圧力に対しても抵抗して立ち上がるというものである」(『真相 イラク報道とBBC』、NHK出版、2006年6月)
ここにもジャーナリストの気骨を感じます。自分の国の政府が、戦争に突っ込んでいくときに、BBCが断固たる批判の論陣をはるわけですから、それは、たいへんな覚悟がいったと思います。
フランスのル・モンド紙―人権宣言を引いて富裕税を迫る
フランスのメディアについても、紹介しておきましょう。これは、現在進行中の問題ですが、メディアが富裕層・大企業課税のキャンペーンをはり、富裕層・大企業に甘いサルコジ政権を正面から批判しています。フランスに「ル・モンド」という有名な新聞がありますが、この新聞は、「金持ちに課税を」と題する社説(2011年8月17日付)で次のように主張しています。
「フランソワ・フィヨン(現首相)は、法人税の課税ベースに『受け入れられる水準を超えた』企業の重役たちの収入も算入することを提案し、ジル・キャレース(国会議員)は、課税所得100万ユーロ以上の3万人の収入に1~2%を課税する新たな直接税を導入するように提案している。両方とも、大資産に課税するということだ。最近の富裕税改革で、大資産家の負担を20億ユーロも軽減したニコラ・サルコジがこれを決断するだろうか? 大統領が二の足を踏んだなら、税負担は『すべての市民が、その能力に応じて、等しく割り当てられる』べきだということを彼に思い起こさせてやろうではないか。ウォーレン・バフェットを引いているのではない。1789年の人権宣言の第13条を引用しているのだ」。
この社説にも、ジャーナリストの気概を感じます。「大統領は富裕税に消極的だ。それなら人権宣言を突きつけてやろう」。たしかに1789年の人権宣言の第13条には、「共同の租税は、すべての市民の間で、その能力に応じて、平等に分担されなければならない」と書いてあります。この歴史的立脚点に立って、政府に富裕税を堂々と迫っていく。
アメリカ、イギリス、フランスのメディアについて見てきました。それぞれなりに、いろいろな制約や問題もあるでしょうが、「権力のチェック機関」としての責任を果たすという点で、ジャーナリズムとしての気骨、気概が強く感じられるではありませんか。
日本の巨大メディア―「権力のチェック役」という役割を果たしているか
それでは、日本はどうでしょうか。
私は、日本の巨大メディアのなかにも、個々には真実を勇敢に伝えようとがんばっている多くのジャーナリストがいることを、知っています。また、個々の論説などのなかには、ときに事実と理性に立ったものも、見られます。それから地方新聞からは、良識の声をしばしば聞きます。
しかし、大手5紙などの巨大メディアを全体として見た場合に、「権力のチェック役」というジャーナリズム本来の仕事を果たしているといえるでしょうか。アメリカやイギリスの新聞やテレビがやったように、社運をかけて、国の進路の根本にかかわる問題を取り上げ、時の政権を覆す気概をもって論陣をはったことがあるでしょうか。
「権力のチェック役」どころか、逆に、財界やアメリカの意向をそのまま受けて、「何をもたもたしているんだ。もっとしっかりやらなくてはだめじゃないか」と尻をたたく、悪い方向に「チェック」する役割を、いまや巨大メディアは果たしているのではないでしょうか。
日本の大手メディアの歴史的弱点―侵略戦争、日米安保、原発列島
なぜそういう実態になっているのか。私はまず、日本のメディアの、歴史的な弱点を指摘しなければなりません。
日本の大手新聞は、日本軍国主義が侵略戦争をすすめた時期に、戦争賛美と、「聖戦への国民の動員」の旗をふりつづけました。真実をねじまげ、戦争礼賛の記事によって、販売部数を拡大し、国民世論を誤った方向に導いた。その責任はきわめて重大です。ところが、敗戦をむかえた1945年、各新聞は、みずから侵略戦争を賛美し、加担してきた事実への真剣な反省をしないまま、しかも、戦前・戦中の旧経営陣の多くが居座ったまま、戦後も新聞を発行しつづけました。
たとえば、「朝日」は、敗戦直後の1945年11月7日付の紙面で、「宣言 国民と共に立たん」なる文書を発表して、経営陣の「辞職」と国民への「謝罪」をおこなっています。しかし、「辞職」したはずの村山長挙社長以下の重役らは、数年後に復帰しています。「読売」は、1945年12月、正力松太郎社長がA級戦犯容疑者として逮捕されますが、2年後には釈放され、日本テレビの社長、「読売」の社主として、新聞メディア、放送メディアの双方に「君臨」していきます。
ドイツと比較すると、日本の新聞の無反省ぶりは対照的です。ナチス・ドイツの侵略戦争に協力したドイツのメディアは、米英仏ソの連合軍によって、いっさい存続させない方針がとられ、それらのメディアは全部つぶされたといいます。そして厳重な資格審査のもとに、戦争責任で汚れていない関係者に、戦後ドイツのメディアの創始、復活をゆだねるということをやったといわれています(『マスコミの歴史責任と未来責任』、日本ジャーナリスト会議編、1995年)。
ところが、日本では、朝日新聞にしても、読売新聞にしても、毎日新聞にしても、戦前以来の名前すら変えないで、恥ずかしげもなく、戦後スタートしたわけです。侵略戦争に協力した政党―政友会、民政党、社会大衆党なども、まともな反省はなかったけれども、過去の名前は恥ずかしくてそのまま使えず、名前を変えて再出発せざるをえませんでした。ところが、大手新聞は名前すら変えていないのです。そういう問題点が戦後の出発点でありました。
そういう出発点ともかかわって、日本の大手メディアが、決定的な場面で、国民の利益に背く行動をとってきたことを、指摘しないわけにはいきません。たとえば、1960年、安保改定阻止闘争が大きく高揚した時期に、一部の暴力集団が挑発的行動を起こしたことをとらえ、6月17日、大手新聞が連名で「7社共同宣言」―「暴力を排し議会主義を守れ」を発表し、与野党をこえて「事態収拾をはかれ」という。これを機に、それまで安保反対闘争の熱気を伝えていた大手新聞は、いっせいに水が引くように尻すぼみとなり、国民的運動の発展に冷水をあびせる役割を果たしました。
それから、これは昨年の党創立89周年記念講演「危機をのりこえて新しい日本を―震災、原発、日本の前途を語る」で話しましたが、1970年代には、電力業界に買収され、原発推進のキャンペーンにすべての大手新聞が軒なみ連座したという歴史があります。私は、財界、政界、官僚、御用学者、巨大メディアによる〝原子力村のペンタゴン〟によって、原発列島化がすすめられたと告発しました。今日の深刻な事故を引き起こした責任の一端を、巨大メディアも負っているわけです。原発事故のあと、巨大メディアがその責任を本格的に自己検証したといえるでしょうか。ここでも自分が犯した報道への真剣な反省があるとは、到底いえません。
それでも、日本のメディアは、1970年代の前半ごろまでは、公正な報道、「権力のチェック機関」という点から見て、積極的な活力もありました。
たとえば、毎日新聞が1968年から69年に企画した安全保障問題の政党討論会です。5つの政党に「組閣」をさせ、他の4党が「野党」になって質問をおこなうという方式で討論がおこなわれた。この企画では、5つの政党を国会の議席に関係なく平等に扱って、おこなわれました。当時、日本共産党の衆院の議席数は5議席でしたが、まったく平等に扱った。共産党の「内閣」の顔ぶれは、「首相」となった宮本顕治さん、「閣僚」となった不破哲三さん、上田耕一郎さんは、そろって当時は非議員、国会議員は松本善明さん、渡辺武さんの2人でした。それでも「共産党への質問戦」も同じように平等に扱われ、毎日新聞の紙上で長い連載となりました。
また、1960年代の末から70年代の前半にかけて、日本共産党が国政選挙で躍進を重ねると、政界に新風を吹き込んだ日本共産党の活動に、メディアも大きな注目をよせ、事実を事実として受け止めた報道をおこないました。
さらに、1973年の田中角栄内閣のときの小選挙区制の企てには、ほとんどのメディアが、「民主主義に反する」として批判的キャンペーンをはり、小選挙区制の策動を許しませんでした。そのころあたりまでは、いろいろな弱点をもちながらも、健全さを発揮した時期もあったのです。
権力と巨大メディアの一体化―決定的転機は小選挙区制だった
それが、大きく変化していきます。1970年代後半から80年代にかけて日本共産党封じ込めの反共キャンペーンがおこなわれ、とくに1980年の「社公合意」を転機に、日本共産党をのぞく「オール与党」体制がつくられると、そのもとで、権力とマスコミとの癒着が強まってきます。
その決定的な転機になったのは、1990年代の小選挙区制導入だと思います。このときに、政府の諮問機関として第8次選挙制度審議会がつくられますが、そこに主要メディアの幹部を軒なみ組み込んだのです。この審議会は、27人の委員中、メディア関係者が12人にものぼりました。
(注)第8次選挙制度審議会に参加したメディア関係者は、次の通りです。新井明・「日経」社長、内田健三・元共同通信論説委員長、川島正英・「朝日」編集委員、清原武彦・「産経」論説委員長、草柳大蔵・評論家・元「産経」記者、小林與三次・「読売」社長・日本新聞協会会長、斎藤明・「毎日」論説委員長、中川順・日本民間放送連盟会長・テレビ東京会長、成田正路・NHK解説委員長、播谷実・「読売」論説委員長、山本朗・中国新聞社長、屋山太郎・評論家・元時事通信解説委員。
第8次選挙制度審議会は、1990年に小選挙区制導入の答申を出します。自分が参加していっしょになってつくった答申ですから、その答申通りに、「政治改革=小選挙区制」という大キャンペーンが、主要メディアのすべてをのみ込んで展開され、小選挙区制導入への道が敷かれていきました。
同じ時期に、1992年、小選挙区制推進の運動体として「民間政治臨調」(「政治改革推進協議会」)がつくられます。ここにも主要メディア関係者が入ります。財界関係者といっしょに、席を並べて参加しました。
そして1993年の総選挙では、「自民か、非自民か」という大キャンペーンがやられました。あのときに、テレビ朝日の椿貞良報道局長が、「非自民政権が成立するように報道せよ」と指示し、日本共産党に「公正な時間を、公正な機会を与えることは、かえってこれはフェアネス(公正)ではなくなる」などとして、テレビを使った世論誘導をおこなったことがあとで大問題になっていきますが、巨大メディアはそこまでいくわけです。
私は、この時期にはじめて国会議員となりましたが、最初の質問が1993年10月の予算委員会での総括質問でした。テーマは小選挙区制で、相手は細川護熙首相でした。「小選挙区制が大政党有利に民意を歪めるか」という私の設問に対して、首相は、いろいろなやりとりのなかで、「民意を歪める」ということを認めたのです。ところが、どの新聞もこの質問戦についてまともに報道しなかった。そのことを思い出します。そして、小選挙区制の導入の強行ということになっていきます。
「民間政治臨調」は、その後、1999年に「21世紀臨調」(「新しい日本をつくる国民会議」)と名前を変えていきます。その「趣意書」を見ると、「国のあり方の改革と未完の政治改革とを『車の両輪』と位置づけて活動を進める」と書いてあります。このように国家改造の「運動体」であることを公然と宣言して活動をおこなってきました。「未完の政治改革」は、のちにだんだんと具体化されてくるわけですが、「二大政党づくり」の動きとなりました。財界と一体になって、2002年から2003年に本格的にはじまる「二大政党づくり」「政権選択選挙」という大キャンペーンを、巨大メディアはあげておこないました。
「21世紀臨調」とはどういう構成かと調べますと、155人の運営委員のうち73人が大手メディアの関係者です。「物語で読む21世紀臨調」によると、「21世紀臨調」とは、「何よりも改革実現のための運動体」であり、「(数々の提言を)公表するにとどまらず、マスメディアを通じて日常的な世論形成を行い、……改革を具体化し実現していくことに最大の力点が置かれた」とあります。巨大メディアを、自分たちに都合のよい世論形成の手段として利用することが、あからさまにのべられています。
公正、公平、独立というジャーナリズムの根本精神がきびしく問われている
こうして、日本における巨大メディアと権力との癒着、一体化は、行き着くところまでいった観があります。
いま熱い問題になっているどの問題をとっても、消費税増税の問題をとっても、TPP参加の問題をとっても、巨大メディアの流している報道は、「権力の監視役」などというものとはおよそかけ離れたものではないですか。「もたもたするな」という「尻たたき役」ではないですか。しかも、そうした国政の根本問題になると、巨大メディアの論調は、驚くほど一色です。相互のチェックが働きません。「独裁」を公言してはばからないような人物を、無批判に、あたかも「改革のヒーロー」であるかのように持ち上げたことでも、巨大メディアの責任は大きいといわねばなりません。
「新聞倫理綱領」では「正確と公正」「独立と寛容」をうたっています。放送法では「政治的に公平であること」「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」を放送事業者に義務づけています。これらにてらしても、いまの日本の巨大メディアの実態は、公正、公平、独立というジャーナリズムの魂を、みずから投げ捨てるものではないか。このことがきびしく問われていると、私は思います。
「しんぶん赤旗」―真実を伝え、希望を運ぶ、かけがえない役割
この状況をどうやって変えていくか。
一つは、あらゆる分野で国民の要求にもとづく運動を発展させることが大切だと思います。現に、原発ゼロ、TPP反対、基地撤去、消費税増税ストップなど、国民の切実な要求をとらえ、政治的立場の違いをこえた国民運動が、多面的に広がっています。このたたかいをさらに広げ、巨大メディアも無視できない流れにしていく。それは、巨大メディアのなかで、ジャーナリストとしての良心をもってがんばっている人々を励ますことにもなるでしょう。
いま一つは、人民的メディアを大きくしていくことです。日本は、アメリカやイギリスやフランスに比べても、巨大メディアが大きな問題をかかえているという話をしてきましたが、私たちは、他の国にはない、日本だけにしかない百万を超える人民的メディアをもっています。それは、「しんぶん赤旗」というメディアです。
私は、「しんぶん赤旗」がいま果たしている役割は、政党機関紙という枠をはるかにこえたものだと思います。国民が、世の中の真実、事実を知りたいと思ったら、日本の問題でも、世界の問題でも、「しんぶん赤旗」は不可欠の存在です。巨大メディアが決して報じようとしない、真実を伝える新聞が、「しんぶん赤旗」であり、またそれは国民にとって、いまの政治と社会の行き詰まりを打ち破る展望はどこにあるのか、希望を運ぶ新聞でもあると思います。
私たちは、こういう素晴らしい人民的メディアをもっているわけですから、その読者の方々を一人ひとり増やし、読者の方々としっかりと結びついていくことがどんなに大切か、その意義ははかり知れないと、私は考えています。この点で、みなさんのご協力を、心からお願いするものです。