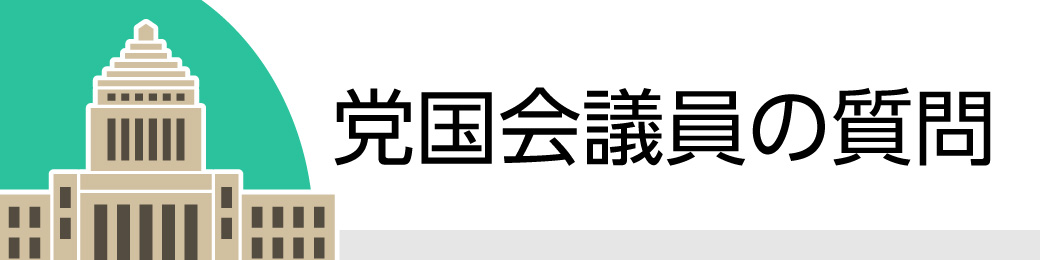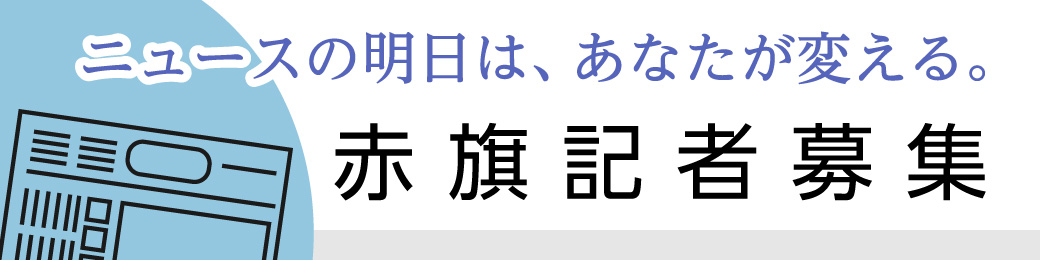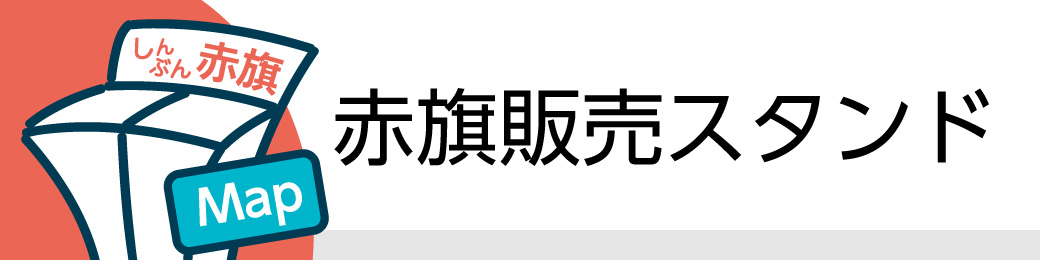2024年6月21日(金)
主張
党首討論 夫婦別姓
個人の尊厳阻み孤立する自民
綱領で、日本の民主的改革の主要な一つに「ジェンダー平等社会をつくる」を掲げている党の党首として、田村智子・日本共産党委員長が就任後初の党首討論で岸田文雄首相に迫ったのが、選択的夫婦別姓制度の実現です。
田村氏は、今国会の参院本会議の代表質問をはじめ、国会質問でつねにジェンダー平等の問題をとりあげてきました。ジェンダー平等が最も遅れているのが国会、政治の分野であり、そこを変えなければならないという認識からです。
■事実を認めながら
田村氏は、日本経済団体連合会(経団連)が政府に選択的夫婦別姓制度の早期実現を要望したことにふれ、「長年にわたる女性たちの訴えがついに経済界も動かした」と指摘。憲法で、個人の尊厳、法の下の平等、婚姻の自由、夫婦平等の権利が掲げられながら、同姓の強制により、実際には姓を変えることの不利益が圧倒的に女性に偏り、女性が個人の尊厳を傷つけられていることについて、岸田首相自身の認識をただしました。
岸田首相はビジネスの面で「そういった事実があることは強く認識している」と認めながら「さまざまな角度から議論する必要がある」「世論が割れている」として「議論を深める必要が今まだある」と後ろ向きの態度に固執しました。
岸田首相は「世論が割れている」とします。しかし、NHKの今年4月実施の世論調査では、60代以下の年代でいずれも7割以上が選択的夫婦別姓に「賛成」でした。
■女性にだけ不利益
内閣府の調査(2022年3月)では40代以下の各年代で6割以上が、どちらかが姓を変えなければならないことで、変えた側に「不便・不利益がある」と回答。「ある」とした人の6割が、通称使用を認めるだけでは対処しきれない不利益があると答えています。
現状では、改姓による不利益を被っているのはほぼ女性であり、これは明確な女性差別です。
岸田首相が「家族の一体感にかかわる」とのべていることに対し、田村氏は「特定の価値観の押し付けだ」と追及しました。
前出の内閣府の調査では、「家族の一体感が弱まるか」という問いに、6割が「影響がない」とし、20代以下では7割以上が「ない」としています。同じ姓でないと「家族の一体感がなくなる」というのは、明治時代の民法や家制度の残滓(ざんし)であり、それにしがみつく古い特定の価値観です。
岸田首相はかつて自民党有志議員の「選択的夫婦別氏制度を早期に実現する議員連盟」の呼びかけ人でした。しかし首相になると古い勢力をおもんばかり、あれこれの理由をつけて制度実現に動こうとしません。
国民の意識は変化、前進し、選択的夫婦別姓を求める運動は財界を含めて広がっています。女性の、個人の尊厳を含む基本的人権の侵害を顧みず国民から孤立しているのが自民党です。
田村氏は一刻も早く国会で民法改正の審議を行うよう岸田首相に求めました。
日本共産党は田村委員長を先頭に、個人の尊厳を阻む自民党政権をかえ、夫婦別姓、ジェンダー平等の実現のために奮闘します。