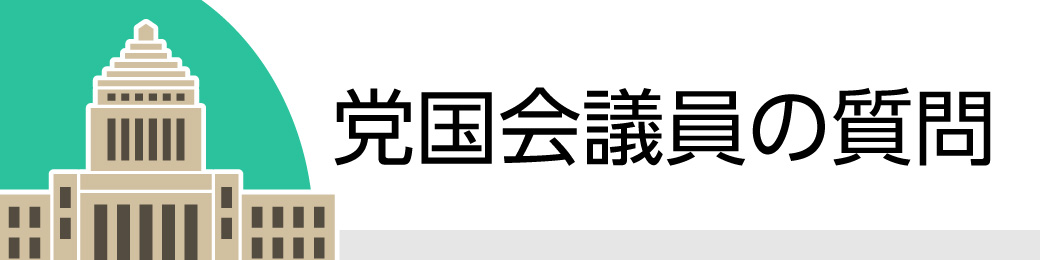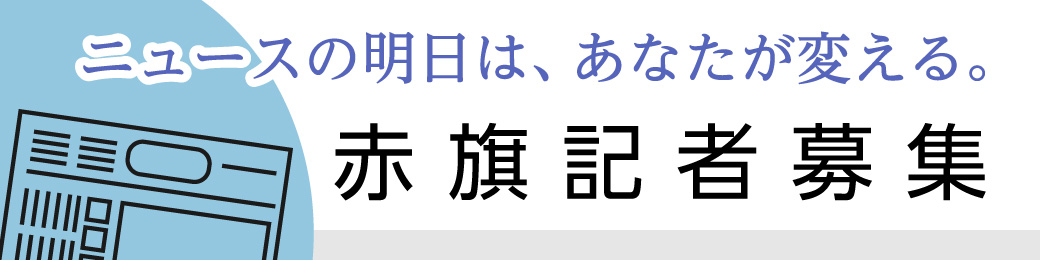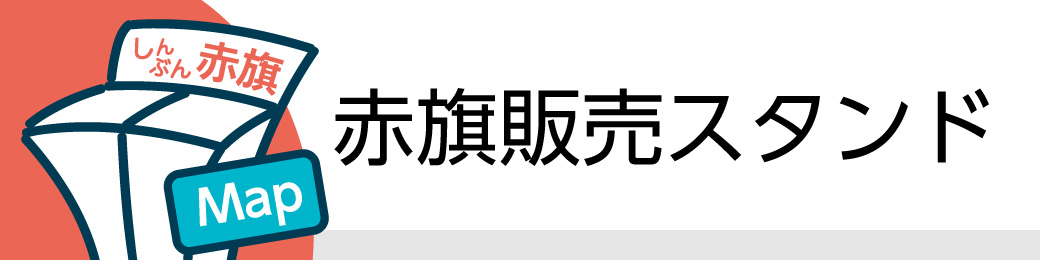2024年6月15日(土)
主張
住民票続き柄記載
同性カップルの生き方尊重へ
同性カップルの生き方を尊重し保障する動きがまた一つ広がりました。長崎県大村市が、同性カップルの住民票で、世帯主と同居するパートナーの続き柄欄に、事実婚カップルに使われる「夫(未届)」と記載したことが5月末に明らかになり、同様の対応を表明する自治体が相次いでいます。11日には東京都世田谷区の保坂展人区長が導入の意向を示しました。導入されれば都内初となります。
国が同性婚を認めないもとで、自治体が公的書類で、男女のカップルと同様の記載を認めた意義は大きく、性的マイノリティーの権利保障の前進です。
■公的書類で認める
住民票の続き柄欄で使う「夫(未届)」「妻(未届)」は、同一世帯の事実婚カップルに適用される表記です。婚姻届を出していない事実婚カップルは、住民基本台帳事務処理要領で「法律上の夫婦ではないが準婚として各種の社会保障の面では法律上の夫婦と同じ取扱いを受けているので、『夫(未届)、妻(未届)』と記載する」と定められています。
大村市は、昨年10月、性的マイノリティーのパートナー関係を公証する「パートナーシップ宣誓制度」を導入しました。今回、この同性カップルが宣誓制度の手続きを済ませていることを確認し、市の裁量として「夫(未届)」の記載を認めました。
パートナーシップ制度は2015年、東京都渋谷区と世田谷区で始まりました。導入が5自治体にとどまっていた18年、政府は「戸籍制度では同性結婚は認められておらず、親族関係があると言えないため、(同性パートナーの)世帯主との続き柄は『同居人』と記載することとしている」と答弁しています(同年6月8日、衆院法務委員会)。
■自治体の動き先行
一方、パートナーシップ制度が広がるなか、同一世帯の同性カップルについて、世帯主との続き柄に「縁故者」と記載できる行政サービスをする自治体が出てきました。「縁故者」は「親族で世帯主との続き柄を具体的に記載することが困難な者」(住民基本台帳事務処理要領)とされます。
昨年10月、県としてパートナーシップ制度を導入した鳥取県では、県内19市町村のうち、鳥取市など12市町が「縁故者」を、倉吉市は「夫(未届)」「妻(未届)」の記載をすでに認めています。同性カップルに「親族関係」を示す「縁故者」や事実婚をあらわす「夫(未届)」「妻(未届)」記載を認める自治体の判断を、政府は黙認せざるをえませんでした。
パートナーシップ制度は人口の85%を占める地域に広がっています。
犯罪被害者遺族への国の給付金をめぐって、最高裁は3月、同性パートナーも遺族と認める判断をしています。事実婚に認めている公的保険や年金など各種の社会保障の権利を同性カップルに保障すべきです。
パートナーシップ制度や今回のような住民票の記載は、長い間の要求で個別に少しずつ実現したものです。これらを一気に解決するのは異性婚と同様に法的に同性婚を認める「結婚の平等」です。同性カップルが真に求めているのはその実現です。