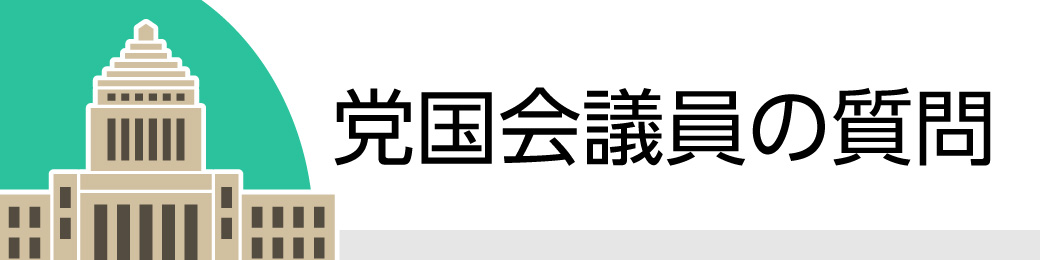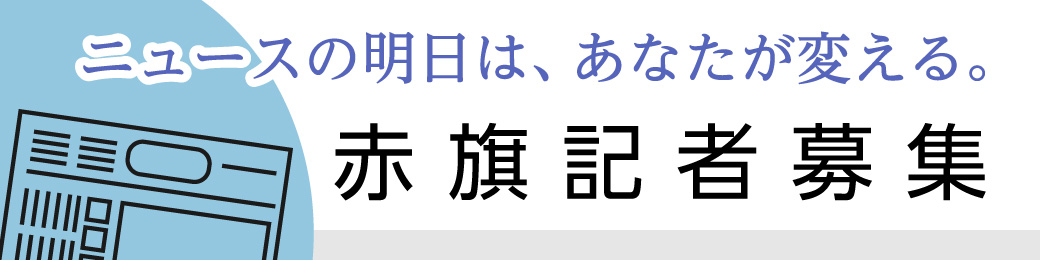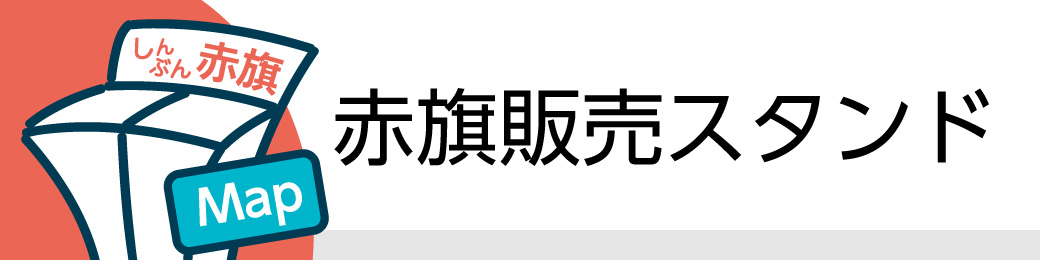2024年6月9日(日)
主張
二酸化炭素の貯留
危険で不確実 脱炭素に逆行
政府が、脱炭素の「切り札」として進めようとしているのが、発電所や石油精製所などから排出される二酸化炭素(CO2)を回収・輸送して地中に貯留する技術(CCS)です。今国会では自民・公明・立民・維新・国民などの賛成多数でCCSの事業化を促進する新法が成立しました。
しかし、CCSには安全性・経済性・実現可能性などで重大な問題があります。政府は2050年に温室効果ガス排出を実質ゼロにするのにCCSが不可欠だとしますが、脱炭素に取り組むかのように装って、大手電力会社などが50年に向け化石燃料を使い続ける仕組みをつくるものです。
■漏出で中毒事故も
国は「先進的CCS事業」として苫小牧、東新潟地域など7案件をモデル事業として選定し、集中的に支援を行いますが、米国ではパイプラインの破断で高濃度のCO2が漏れ多数の住民が病院に運ばれる事故が起きています。地震などで漏れないよう長期の管理も必要です。地中深くCO2を圧入すること自体、環境に大きな負荷を与えるもので、地震誘発リスクも指摘されていますが、環境アセスメントの適用外です。
三井物産がすすめる、近畿・九州地域の化学・石油精製など複数産業で排出されるCO2をマレーシアへ輸送・貯留する事業計画では、現地NGOが「途上国へのCO2輸出は重大な気候不正義」と強く抗議しています。
事業化を優先して住民の命、周辺環境、将来世代への影響に関わる安全規制を後退させてはなりません。
■巨額の国費を投入
CCS事業は今後10年間に官民で4兆円の投資を見込んでいますが、法整備を要望した業界自らが「技術確立にかかる不確実性が高く、多額の投資が必要となる一方、リスクも非常に高い」と述べています。
海外では資金が集まらず中止や延期になった事業が多いのが現実です。米国の会計検査院は、政府が補助金を出した火力発電CCS8件中7件が失敗したと報告。残りの1件も不調で、米国企業がエネオスの子会社に譲渡した案件です。
CO2を確実で安定的に分離・回収、輸送、貯留する技術は確立していません。国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書統合報告書もCCSはCO2削減策としては非常に高コストで可能性が低いとしています。
高リスクで経済性がない事業に巨額の国費を投入して民間投資を促し、ツケを電気代や税金として国民に転嫁するようなことは、到底認められません。政府は、安価で導入可能性も高い再生エネルギーへの転換が容易な発電分野さえもCCSの対象にしています。
前出のIPCCの報告書は、この10年の選択や対策が数千年先まで影響すると警鐘を鳴らし、2030年までに温室効果ガスを大幅かつ早急に削減する必要があるとします。CCSの事業化の目標期限は30年であり、30年までの温室効果ガス削減にはまったく役に立ちません。
石炭火力発電の廃止期限を定め、徹底した省エネ、再エネに予算と施策を集中し、将来世代に対し責任が持てるエネルギー政策への転換が求められています。