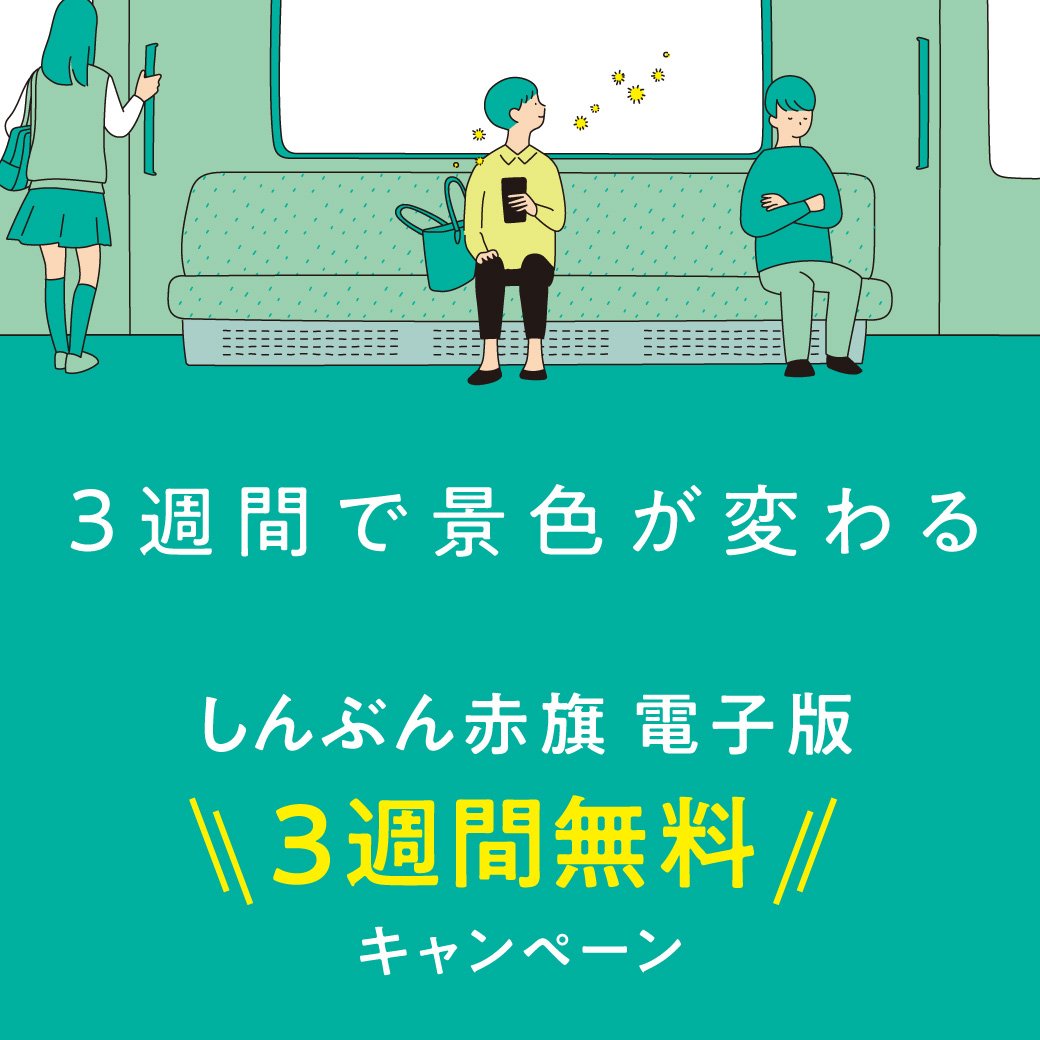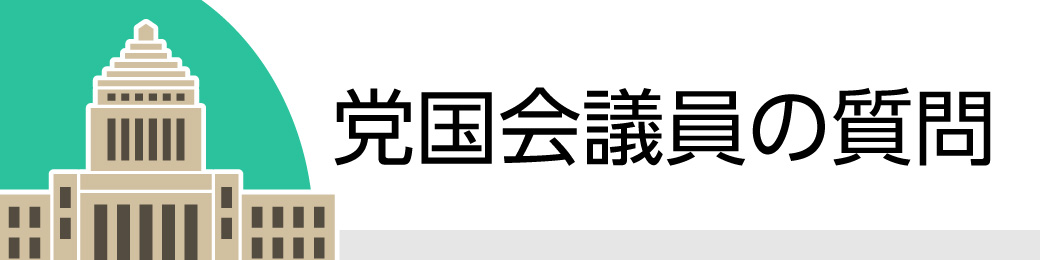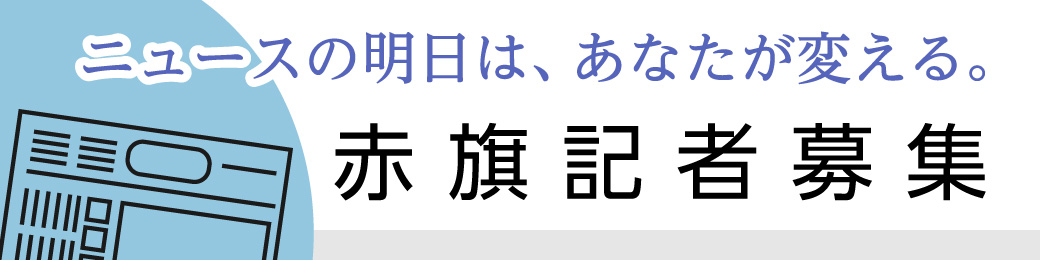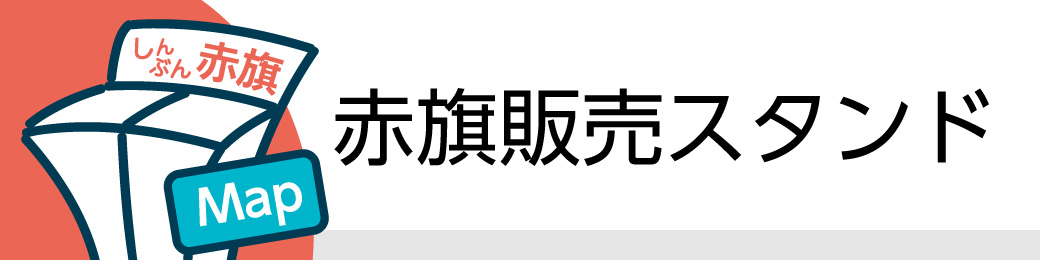2024年6月8日(土)
麦・大豆など増産 本腰を
紙氏、選択的拡大と自由化批判
参院農水委
 (写真)質問する紙智子議員=5月28日、参院農水委 |
日本共産党の紙智子議員は5月28日の参院農林水産委員会で、政府が食料安全保障の確立と言うなら、選択的拡大や自由化によって、麦や大豆の生産を切り捨てた過去の政策を反省し、麦、大豆などの増産に本腰を入れるよう求めました。
耕地利用率(耕地面積に占める作付延べ面積の割合)は米と麦などの二毛作が行われていた1950年代には130%を超えていましたが、その後10年間で20ポイント減少し、2022年には91%に減りました。紙氏は、1961年の旧農業基本法が選択的拡大政策(米麦から果樹、畜産への切り替え)を進めたことから減少したと指摘し、それへの反省はあるかと質問。農水省の平形雄策農産局長は「昭和30年代から40年代の半ば、麦、大豆の作付面積は激減した」と認めましたが、「選択的拡大政策が耕地利用率の低下の要因だと一概に言えない」と開き直りました。
紙氏は、世界貿易機関(WTO)協定の小麦の輸入枠は547万トンで、新たに環太平洋連携協定(TPP)枠や日EU(欧州連合)EPA(経済連携協定)枠をつくり、小麦の輸入枠を増やしているのに、国産が増やせるのかと追及。平形局長は「輸入先国からの理解を得ながら国産の増産に取り組みたい」と答えました。紙氏は「避けて通れない課題だ。国産増産の本気度が問われる」と指摘しました。
紙氏は1960年から小麦の単収の伸びはフランスやドイツと2~3倍の差が開き、農水省の元研究者が選択的拡大政策で麦は軽視され、研究室や研究員は半減したと語っているとして、選択的拡大政策は小麦の品種改良も遅らせたのではないかと質問。同省の川合豊彦技術総括審議官は「限られた予算のなかで頑張っていきたい」と答えざるを得ませんでした。