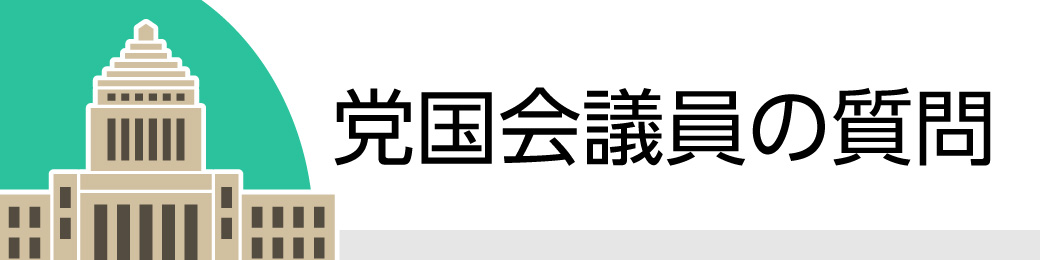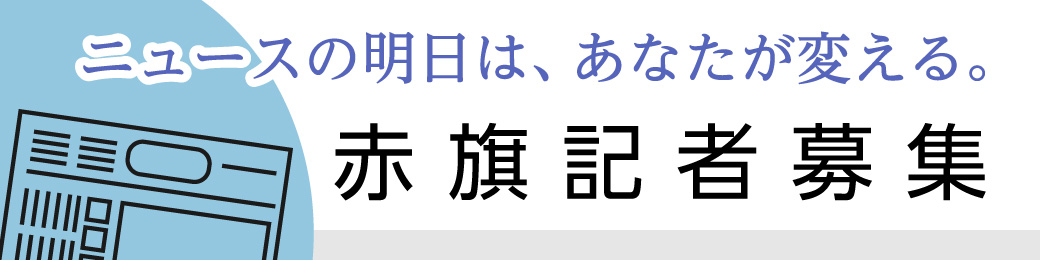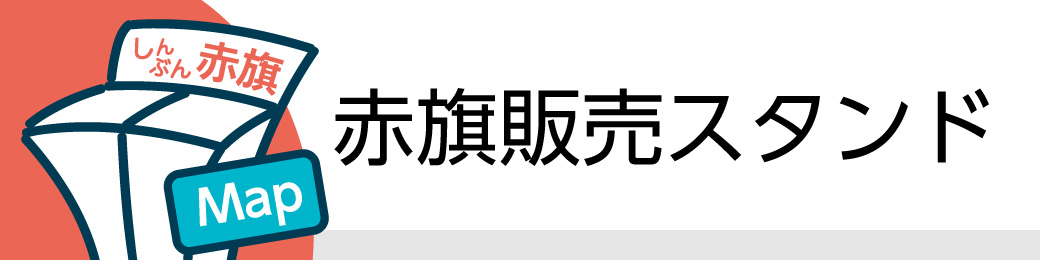2024年5月20日(月)
子ども・子育て支援法改定案
吉良議員の質問(要旨)
参院本会議
日本共産党の吉良よし子議員が17日の参院本会議で行った子ども・子育て支援法改定案についての質問の要旨は次の通りです。
子ども・子育て支援金制度はなぜ、社会保障のみが財源の対象なのでしょうか。政府は、社会保障以外の財源は「防衛力強化のための財源」と明言していますが、子ども・子育て支援よりも軍事優先ということではありませんか。
総理は子ども・子育て支援金により「実質的な負担はない」と言いますが、本法案によって年1兆円の支援金が医療保険料に上乗せされ全国民から徴収されます。逆進性のある医療保険から財源を持ってくるのは全くの筋違いです。
所得が同じでも入っている保険によって支援金の負担が変わることも不公平です。低所得者が多い国民健康保険の方が、他の被用者保険に比べ、支援金の負担が重くなります。今回の支援金が、社会保障の所得再配分機能を弱め、格差と貧困に悪影響を及ぼすのではありませんか。
今回の法案は、子ども関係以外の社会保障予算について、2023~28年までの6年間で保険料と公費支出分あわせて2・1兆円も削減するとしています。高齢者向けの支出を削って子ども関係支出を増やすやり方そのものが、社会連帯を壊し、世代間の分断と対立をあおるものです。
「こども誰でも通園制度」の試行事業では、利用する園、月、曜日や時間を固定せず利用する自由利用方式を採用でき、1時間ごとに事業者を変えることも可能です。全国どこでも利用の直前までアプリで予約ができるようにすると言いますが、子どもが新しい環境や人に慣れるための「ならし保育」の時間すらとれません。自由利用方式は、子どもにとっても、施設にとっても通常保育とは異なる困難や負担があることを認めますか。
保育所における死亡事故の発生は0~2歳児、預け始めの時期が最も多く、常に子どもを受け入れることになる「こども誰でも通園制度」で子どもの安全は保障されるのか。保育の質と安全の保障の前提となる人員配置基準も保育士が半分で良いとされました。通常の保育より難しい保育が保育士側に求められるにもかかわらず、なぜ人員配置は低い水準で良いと考えたのか。「こども誰でも通園」というのであれば、親がどれだけ働いているかなどで対象をしぼる「保育の必要性」の要件を見直して、全ての子どもたちに、質の確保された保育を保障できるようにすべきです。
若者、子育て世代の経済的負担の軽減、ジェンダー不平等の解消、なにより、全ての子どもたちが、ストレスのない安心安全な環境で、自由に遊び、自由に学べる権利を保障することこそが政治の責任です。