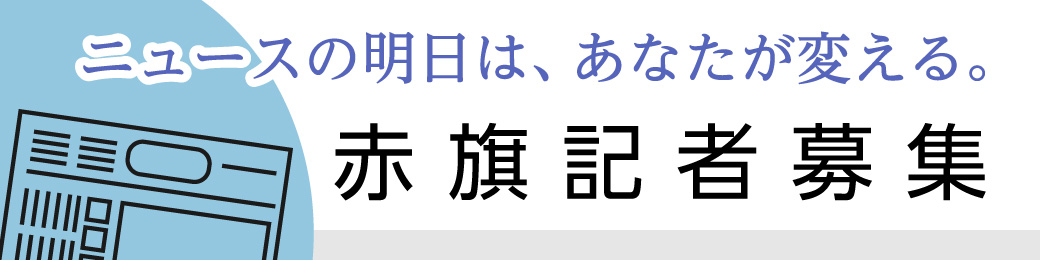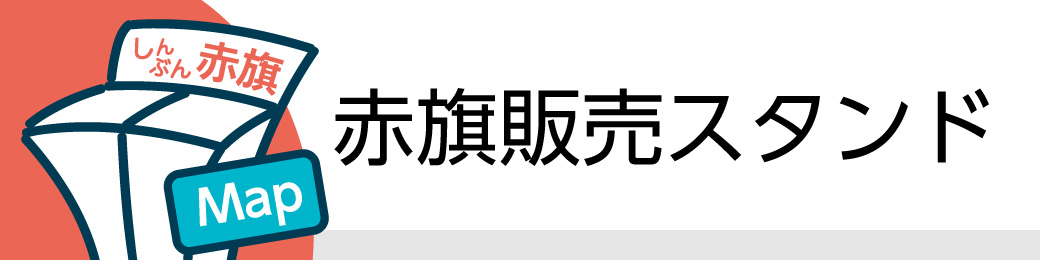2022年10月2日(日)
記者座談会 「日本共産党100年の歴史と綱領を語る」を読む(3)
自己改革 その最大のものは
「50年問題」と自主独立路線の確立
 (写真)記念講演する志位和夫委員長=9月17日、党本部 |
A 100年の党史を貫く第二の特質は、「自己改革」だね。それも「科学的社会主義を土台にした自己改革の努力」。政治路線と理論の面でも、党活動と組織のあり方の面でも、つねにその努力を続けてきたことだ。
B 反共論者らは日本共産党を「無謬(むびゅう)主義の党」―“誤りを決して認めない党”と攻撃しているけれど、「自己改革の努力」をみれば、これほど事実に反する的外れな攻撃はないことがわかるね。
C 志位さんは、その最大のものが、「50年問題」の危機をのりこえて、自主独立の路線を確立したことだと位置付けている。「50年問題」とは、戦後間もない1950年、旧ソ連のスターリンと中国によって武装闘争を押し付ける乱暴な干渉が日本共産党に対して行われ、党が分裂する事態が起きた党史上最大の危機だ。志位さんは「この危機を乗り越える過程で、わが党は大きな自己改革をとげました」といっている。
D 実感としてなかなかわからないけれど、当時の記録をみると、分裂のなかで不当な除名が行われたり、活動から排除されたり、党組織も党員も深く傷ついたことが記録されている。戦前の苛烈な弾圧を体験した宮本顕治さんが、それを上回る「最大の悲劇的事件」と述懐するほどの深刻な危機だったんだね。
A 講演では、この無法な干渉に反対し、党の分裂を克服して統一を実現し、日本の党と運動の問題は日本共産党自身がその責任で決めていくという「自主独立の路線」を確立した経過が生々しく示されている。
C そのプロセスで大事だと思ったのは、干渉を批判できるかどうか、ここが試金石だったということだ。そのことを志位さんは「『50年問題』は、ソ連などによる干渉が引き起こしたものであり、干渉に対する批判なくしてその科学的総括は絶対にできません」とのべている。だいたい、ソ連や中国は日本共産党が「50年問題」を総括することそのものに反対したというんだからね。
A 当時のソ連がもっていた“権威”を考えると、干渉を毅然(きぜん)と批判することは並大抵ではなかったと思うよ。それを乗り越えて、1957年10月の第15回拡大中央委員会総会で総括文書「50年問題について」を採択したんだね。ソ連の干渉は50年と51年の2度あったんだけれど、2度目の干渉について、党の「正しい統一の道をとざした」と批判を明記した。これが自主独立の出発点となっていった。
干渉とのたたかい通じ全党の血肉に
 (写真)(左から)ソ連共産党中央委員会の書簡(1964年4月18日付)にたいする日本共産党中央委員会の返書(「アカハタ」1964年9月2日付)、ソ連共産党の解体にたいして出された日本共産党常任幹部会の声明を掲載した「赤旗」1991年9月2日付、日中両党の関係正常化を報じる「しんぶん赤旗」1998年6月12日付 |
C 党はこうして、1958年の第7回大会で自主独立の路線を確立するわけだが、志位さんは「それがどれだけ自覚的につかまれているか、個々の幹部にも違いがあった」と率直に言っている。それが全党の血肉となっていくのは、1960年代以降のソ連、中国の二つの覇権主義による乱暴な干渉とのたたかいを通じてであった―ここも大事なポイントだね。
D 志位さんは、このたたかいは、党中央が干渉者と論争していただけではない、全党が懸命に論争の中心点をつかみ、全党の力で干渉を打ち破っていったのだということを、長大論文が掲載された当時の「赤旗」も示しながら語った。そうやって、全党は鍛えられ、認識が発展し、自主独立の路線が血肉となっていったんだね。
B よく、そんな長大論文を当時の党員は読んだものだねという人がいるけれど、志位さんが紹介しているように、当時は国内に干渉者に内通した分派=「ニセ共産党」がつくられ、党攻撃をしてきていた。そして少なくない他の党が干渉者に追随・加担し、メディアも日本共産党がソ連と論争すれば「中国派」だといい、中国とも論争すると「自主孤立」とやゆしたというんだから、こういう状況のなかで活動しようと思えば、理論を必死に身につけなければならなかったんだね。
C 当時、滋賀県委員会で活動していた浜野副委員長の体験も紹介されているけれど、文字通り「むさぼるように」読んだんだね。
A 私がなるほどと思ったのは、ソ連、中国の干渉とのたたかいは、日本共産党だけの問題じゃなかったという指摘だ。志位さんは、「わが党への干渉は、日本国民の運動の自主性に対する侵害であり、それは日本に対する主権侵害・内政干渉という重大な意味をもつ」と強調している。
D この指摘は本当にはっとさせられた。もし万が一、日本共産党が“ソ連や中国の手先の党”になってしまったら、その“手先”を通じて日本の内政に干渉することになる。当時の全党の先輩たちの奮闘で干渉を打ち破ったことは、日本への内政干渉を許さなかったという国民的意義をもっているね。
B 干渉をはね返して、ソ連、中国という二つの大国の党に「二つながら干渉に対する『反省』を言わせた世界で唯一の党が日本共産党であります」というくだりは誇らしかった。旧ソ連や中国の問題を利用した反共攻撃などにたいして、最も痛烈な反論になると思った。
(つづく)