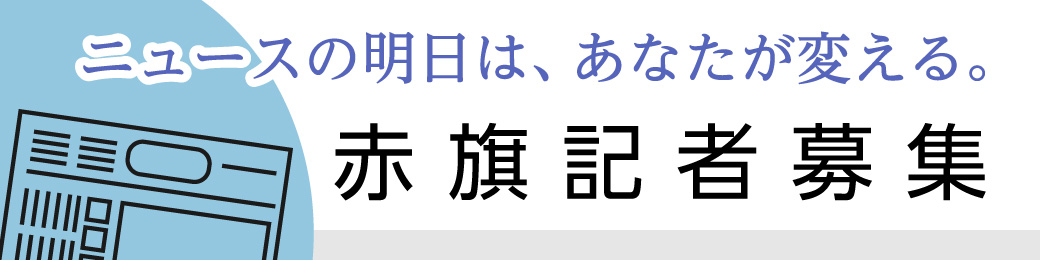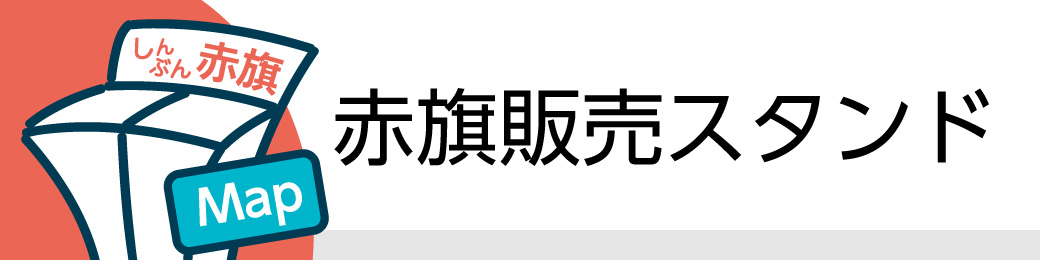2019年2月18日(月)
主張
少年法の適用年齢
引き下げる理由は一つもない
民法の成年年齢が18歳に引き下げられるのにあわせ、少年法の適用年齢を20歳未満から18歳未満に引き下げるかどうかの検討が、法務大臣の諮問機関である法制審議会の部会で進んでいます。適用年齢の引き下げが日本社会にもたらす弊害は、あまりに大きいと言わなければなりません。引き下げありきで議論をするのでなく、少年法が果たしている役割について、改めて国民的な議論と理解を深めることが求められます。
“甘やかすな”は誤解
「少年だからといって甘やかさずに、罪を犯した者は厳しく罰するべきだ」と適用年齢の引き下げを主張する意見があります。しかし、これは大きな誤解です。
少年事件の多くは、過失運転致死傷・道交法違反、万引き、けんかなどによる傷害です。成人の犯罪なら被害金額の多寡や示談の成否などが酌量され、多くは不起訴や罰金刑、執行猶予付きとなります。一方、少年の場合は軽微な犯罪や非行も含め、全ての事件を家庭裁判所に送致し(全件送致主義)、家裁や少年鑑別所での科学的な社会調査と資質鑑別の結果をふまえて一人一人に対する処遇を決定します。成人ならば服役しない軽微な犯罪でも長期に少年院に収容となるなど、成人より“厳しい”処分となるケースもありえます。
2017年の少年被疑者は約6万4千人、うち18、19歳が約3万6千人と半数以上を占めます(犯罪白書)。適用年齢を引き下げれば、これだけの規模の若年者が少年司法の手続きから外れます。罪を犯した少年を「厳しく罰する」どころか、反省と再犯防止・立ち直りに向けた十分な処遇を行わないまま放置することになります。
非行少年は、その多くが成育環境や資質・能力にハンディを抱えています。少年院在院者の7割以上が家族などから虐待や暴力を受けた経験を持つとの調査もあります(法務総合研究所、01年)。こうした少年たちが更生し、社会に適応して自立していくうえでは、刑事訴訟的な判断だけでなく、個々の少年への福祉的・教育的な関わりが必要です。現行少年法のもとでの全件送致主義は、そのための有効な仕組みです。
適用年齢が引き下げられれば、それを口実に少年犯罪の防止と少年の更生に取り組む体制が大幅に弱体化される懸念もあります。少年犯罪は実数でも少年人口あたりの発生率でも減少しています。重大事件も減っています。その一方で、貧困と格差の広がり、家庭・地域の脆弱(ぜいじゃく)化、いじめや虐待の深刻化など少年の成育環境は困難さを増しています。“重大な犯罪の芽を小さなうちにつむ”体制を決して後退させてはならず、むしろ充実させることこそ必要です。
法の目的ごとに検討を
「選挙権も民法も少年法も“18歳から成人”で統一すればよい」との意見もあります。しかし、年齢制限は本来、それぞれの制度や法の目的、社会環境などによって検討されるべきです。現に飲酒や喫煙は、健康被害や非行防止の観点から「20歳以上」が維持されました。若者の権利拡大と自立の促進に関わる選挙権や民法と、社会から逸脱した若者の処遇を定める少年法は、法の目的が全く違い、同列に論じられません。
少年法の適用年齢を引き下げる理由は一つもありません。