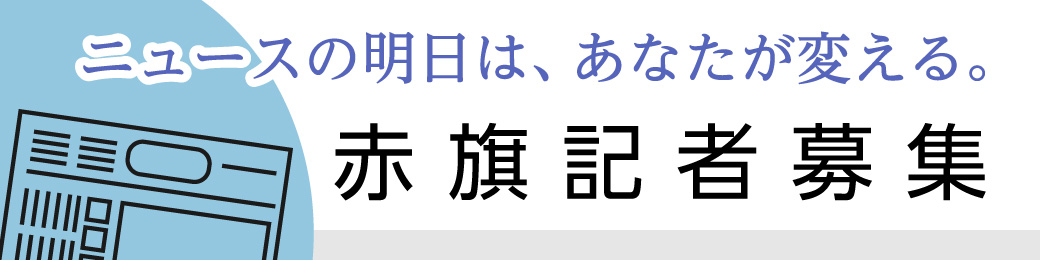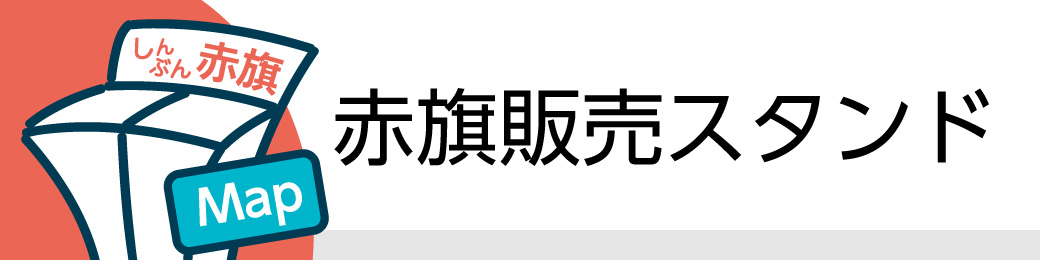2017年3月20日(月)
2017とくほう・特報
戦争にのまれた科学技術者
軍産学共同 旧陸軍登戸研究所は語る
安倍晋三政権のもとで軍事予算が初めて5兆円を超え、兵器研究予算が大幅に増やされました。戦前、兵器開発に科学技術者が動員されたことを教訓に「科学を戦争に使わない」と決意をしてきた人びとが軍事問題とどう向き合うかが問われています。秘密戦・謀略戦を担った旧陸軍登戸(のぼりと)研究所に「戦争と科学者」の問題をみました。
(山沢猛)
 (写真)登戸研究所資料館で展示パネルについて解説する山田館長=3月、川崎市 |
生物兵器を開発
川崎市多摩区の丘の上、明治大学生(いく)田(た)キャンパスにある「明治大学平和教育登戸研究所資料館」―。
「最近の事件で暗殺にVXガスが使われたことが話題になっています。戦前の登戸研究所でも、軍が対人用の青酸ニトリールという無色・無味・無臭の毒薬を開発しました。動物実験にとどまらず、中国の南京まで出張し、中国人の捕虜十数人を死亡させる人体実験まで行いました」
3月初めの見学会で、山田朗(あきら)館長(文学部教授)が、多くの見学者を前に解説します。
資料館自体が、いまも唯一残る秘密研究所時代の建物です。ここで「敵国」の小麦、イネなどの食用作物をいかに効率的に枯らせるかという昆虫・細菌など生物兵器の開発を行っていました。
人間に対する生物化学兵器の開発・製造・実験をしたのが、関東軍防疫給水部、いわゆる731部隊(石井四郎軍医中将の部隊)です。これにたいし登戸研究所は第二科で、植物、家畜を対象にした兵器を研究し、両者は協力しながらも“棲(す)み分け”をしていました。
 (写真)登戸研究所で印刷された偽造法幣。法幣とは中国の蒋介石政権が発行した通貨(資料館提供・渡辺賢二氏寄贈) |
登戸研究所は四科からなります。展示室はそれに沿って、第1「登戸研究所の全容」、第2「風船爆弾と第一科」、第3「秘密戦兵器と第二科」、第4「偽札製造と第三科」、第5「敗戦とその後の登戸研究所」に分かれます。
資料館は4年の準備期間をへて2010年に開館。以後、年間6千~7千人、累計で5万5千人の個人やグループ、団体が訪れました。高校生の集団や、修士論文執筆のために来た大学院生の姿も。
見学者の感想には「入った時から感じる空気の重さ、ぞっとする事実の掲示に胸が痛くなりました。本当に来てよかった」(女性)、「軍事研究がこれほど組織的になされていることに驚いた。日本は戦争の被害者であると同時に、加害者であることを思い知らされた」(男性)などが見られます。
風船爆弾に動員
軍産学共同をすすめた陸軍登戸研究所に、科学技術者はどう関わっていたのでしょうか。
1980年代から、川崎の歴史の掘り起こしをしてきた渡辺賢二さん(当時高校教員)と高校生たちは、地道で粘り強い調査活動を続けてきました。その中で偶然、登戸研究所に勤めていた軍人や技師、地元で雇われた工員・事務員との接点が生まれました。
「高校生の皆さんには話しておきたい」と重い口を開いた一人に、伴(ばん)繁雄氏がいます。
伴氏は終戦時に陸軍技術少佐で、スパイ兵器・生物化学兵器の開発を担った第二科の幹部所員でした。軍功をたたえられて当時の東条英機陸軍大臣から「陸軍技術有功章」を授賞されています。
伴氏が1993年に亡くなる直前に執筆した『陸軍登戸研究所の真実』(芙蓉書房出版)は、研究所の組織をこう描いています。
「所員として理科、工科系諸学校から多数の有能な人材が専門分野別に求められたほか、日本のトップクラスの大学教授や民間企業の技師、研究者が嘱託として研究に参加した。登戸研究所自体製造工場であるが、精巧な器材製作は民間企業が担当することもあった」
「科学技術者が戦争に組み込まれていくプロセスを典型的に示すのが、風船爆弾の開発・製造です」(山田氏)
直径10メートルの気球の風船爆弾は暗号名「ふ号装置」と呼ばれました。約1万発放球され、約1000発がアメリカ大陸に届いたとみられ、361発の着弾が確認されています。オレゴン州ブライで爆弾に触れた民間人6人が命を奪われました。
当初、牛を皆殺しにする牛疫ウイルスを搭載する予定で完成に近づきましたが、米国の同様の反撃を恐れ、断念しました。
高度1万メートル、零下50度の環境で、偏西風にのせて太平洋上空を9000キロメートル飛ばし米本土に落下させるには、偏西風の動き、気温変化など正確な上空気候図の作成が必要でした。
当時、軍にそのような知識はなく、中央気象台(今の気象庁)や、東京大学工学部航空研究所の専門家が引き抜かれました。
第二科の生物化学兵器の開発には、農学系の科学者が動員されました。軍に医者や獣医はいましたが、農業専門家はいないので、農業試験場や品種改良を専門にする人たちを引き抜いて植物を枯らす研究をやりました。
本来、作物を育てる研究者がまったく逆の研究に従事していたのです。
実際に飛行機を使い、中国湖南省の洞庭湖の西側の稲田にたいし、細菌とニカメイチュウ(イネ食害の虫)の散布実験が行われました。
倫理観失う異常
登戸研究所の科学技術者はどういう心境にあったのでしょうか。
それを示すのが、先の伴氏の証言です。
伴氏と所員は1941年6月、中国の南京で約1週間、731部隊の姉妹部隊と連携し、毒物の青酸ニトリールを人体に使いました。致死量、症状の観察には動物でなく、人体実験が必要であるという判断でした。
戦後、この実験の心境を「初めは厭(いや)であったが馴(な)れると一ツの趣味になった。(自分の薬の効果をためすために)」と証言しています。(犯人が毒物で12人を死亡させた1948年帝銀事件での捜査メモ「甲斐文書」)
科学者が戦争に勝つという大義名分を後ろ盾に研究成果を極めようとして、倫理観を失った時、どこまで異常な心理になってしまうかを示しています。
渡辺氏は「伴さんは、自分が登戸で行ったことを戦争に勝つためだったと思う一方、戦後になればそれは単なる人殺しにすぎないという対立の中で最後まで苦しんだ人でした。だから高校生に罪を語ろうとした。私たちとの接点がなかったら『秘密を墓場まで持っていく』ことになったと思います。軍事研究の頂点にあった秘密組織が伴さんのような人々を生み出した。そのことを今の時代に絶対くりかえしてはなりません」と語ります。