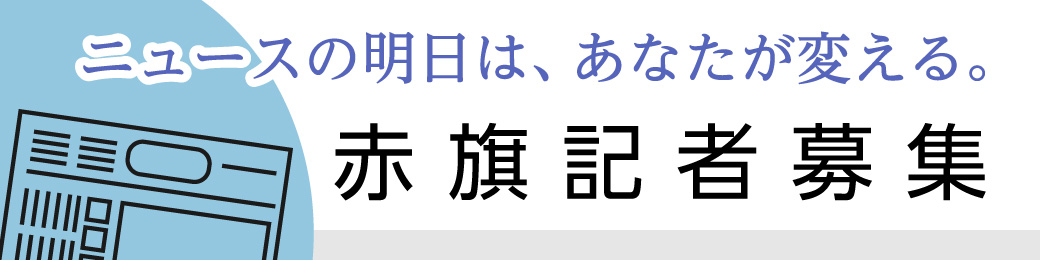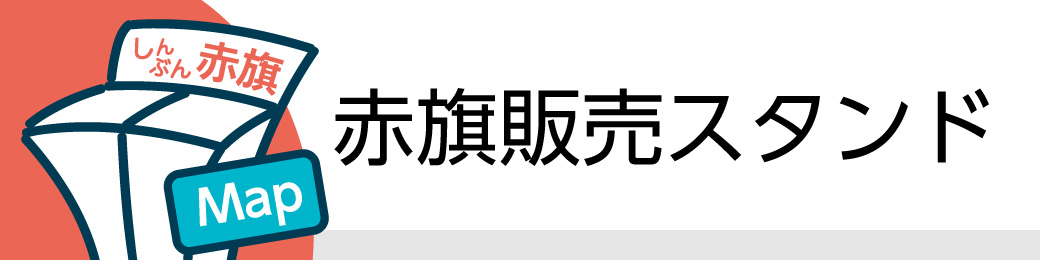2016年10月7日(金)
主張
ノーベル賞に大隅氏
基礎研究重視への転換が急務
ノーベル賞が次々発表され、医学生理学賞は、東京工業大学栄誉教授の大隅良典氏に決まりました。細胞が自分のタンパク質を分解してリサイクルする「オートファジー(自食作用)」と呼ばれる仕組みを解明した功績に対してです。心からの敬意を表します。
地道な探究が希望を開く
私たち生物はタンパク質でできています。人間の体内では、1日に約300~400グラムのタンパク質が合成されます。食事で補給するタンパク質は1日80~90グラムで、残りは、不要になったり、壊れたりしたタンパク質を分解してリサイクルしています。この役割を担うのがオートファジーです。50年前に知られていましたが、その仕組みは未解明のままでした。
謎を解いたのが「人がやらないことを手掛けることが信条」という大隅氏でした。当時は細胞の「ゴミため」と思われ、誰も見向きもしなかった細胞内の液胞に着目。液胞の上澄み液が時々、キラキラと光るのに興味を持ち、「液胞で何か起きているのではないか」と酵母内の液胞を顕微鏡で観測し続けました。1988年、たくさんの小さな粒がピチピチ踊るように跳びはねる現象を発見し、世界で初めてオートファジー現象を肉眼でとらえることに成功しました。さらに、人工的に遺伝子変異を起こした何千種類もの酵母を調べ、93年にはこの働きに不可欠な遺伝子14種類を特定しました。
この発見を機に、世界で年間十数件だった関連論文は、今では約5千件に増加しました。オートファジーは、あらゆる生物に共通する機能であり、がんやアルツハイマー病、糖尿病などの病気との関連が明らかになりました。さまざまな病気の治療につながると期待されています。
地道に真理を探究する基礎研究が、思わぬ展開で有用性をもたらし、人類に希望をひらくことを示しています。大隅氏も「研究を始めたときに、オートファジーが病気や寿命にかかわると確信していたわけではない」と述べています。
自然科学での日本人受賞は3年連続となり、2000年以降の受賞者は米国に次ぐ17人です。日本の基礎研究の水準の高さを示すものですが、その研究成果の発表のほとんどは1970~90年代です。むしろ、今は論文の国際的地位が質量ともに低下しています。
それは、政府が「役に立つものしか、予算をつけない」と「選択と集中」をはかり、大学の基盤的予算をこの12年間で1580億円も削減する一方で、競争的資金を増やして研究者間の過当な競争を強要してきたからです。成果主義が強まり、自由な研究、長期的視点の研究が弱められています。
大隅氏も「大学や研究所の経常的な活動のための資金が極端に乏しくなってしまった」「新しい道の課題に挑戦することが難しい」と憂慮しています。この指摘を政府は重く受け止めるべきです。
過当競争の強要でなく
安倍晋三政権は「成長戦略」の一環として、国立大学の3類型化など「選択と集中」を強め、基盤的な予算の削減を続けています。
こうした政策を見直し、基礎研究を抜本的に振興する方向への転換をはかることは急務です。そうしてこそ、21世紀の日本を支える知的基盤を築き、人類社会の発展に貢献することができます。