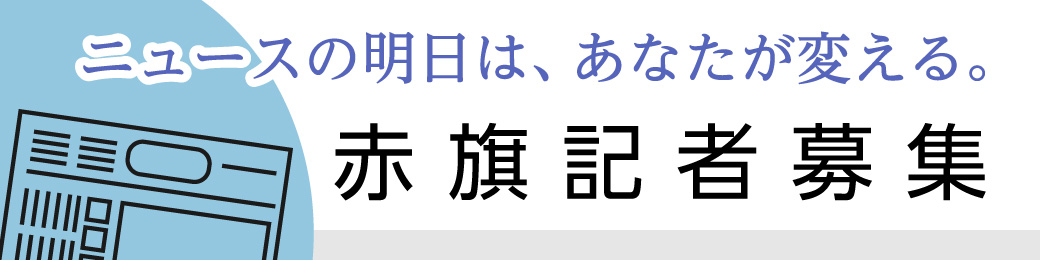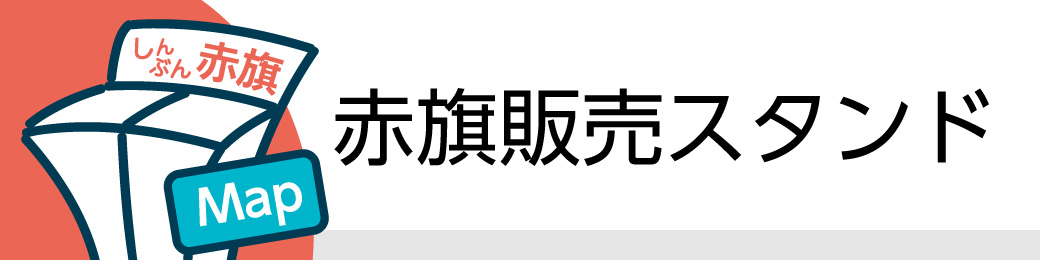2013年12月19日(木)
『古典教室』第3巻を語る(上)
第4課 エンゲルス『フランスにおける階級闘争』への「序文」
マルクス、エンゲルスは、こうして多数者革命論を発展させた
『古典教室』第3巻は第4課で革命論、第5課でマルクス・エンゲルス以後の理論史をあつかいました。講義を担当した不破哲三・党社会科学研究所所長と、石川康宏・神戸女学院大学教授、山口富男・党社会科学研究所副所長の3人が第1巻、第2巻にひきつづいて語りあいました。
「序文」には党綱領の革命路線の基礎づけがある
 (写真)左からから、神戸女学院大学教授石川康宏さん 党社会科学研究所所長不破哲三さん 党社会科学研究所副所長山口富男さん |
―いよいよ『古典教室』第3巻。まず、『フランスにおける階級闘争』(マルクス)へのエンゲルスの「序文」からですね。
不破 われわれが「多数者革命」と言っている言葉は、もともとは、この「序文」からとったものなのです。1976年の第13回臨時党大会で、「執権」問題など綱領の用語改定をやりました。そのとき、エンゲルスの「序文」をあらためて研究して、マルクス、エンゲルスが、革命活動のなかで初期の“少数者”革命から“多数者”革命の路線への発展をやり遂げてゆく歴史をつかみ、私たちの党綱領の立場が「多数者革命」という意義を持っていることを明確にしたのでした。
この「序文」は、それ以後も、ずっと読んだり紹介したりしてきたのですが、今回、これをテキストにして講義をやることになって、あらためて始めから終わりまで読みなおしてみると、これはたいへんすごい論文だという思いをあらたにしました。
マルクスやエンゲルスの著作には、彼ら自身が自分たちの革命思想の発展の歴史を率直にふり返り、その自己点検のなかから現在の視点を明らかにした論文というものは、ほかにはほとんどないのです。しかも、この「序文」では、50年代から60年代にかけて革命観の大転換があったことにくわえて、その時期にマルクスの資本主義観が大きく転換したことにまで言及しています。
 (写真)新日本出版社・1400円(税別) |
このてい談でも、『資本論』の草稿執筆中にマルクスの資本主義観や恐慌論の転換が起こったことについて話してきたのですが、エンゲルスの説明はそれを裏付ける話で、ここでエンゲルスが展開した自己点検の歴史は、経済学などほかの分野の研究の上でも、大事な意味をもってきますね。
マルクスの学説全体のなかでの革命論の位置づけ
石川 不破さんはここで、革命論が科学的社会主義の理論全体の要だということをあらためて強調していますね。それに関連してですが、マルクスの理論には長く「三つの構成部分」という形で紹介されてきた歴史があります。それとこの革命論の関係はどうなっていたのでしょう。
不破 「三つの構成部分」と言いだしたのはレーニンで、1913年の論文なのですが、そのレーニンも、翌14年に「カール・マルクス」というマルクスの学説の全体的な解説に取り組んだ時には、「階級闘争の戦術」、つまり革命論という柱を独自にたてることになりました。レーニンにとっても「三つの構成部分」という整理は不変のものではなかったのですね。
石川さんが前回紹介されたマルクスの言葉に、「哲学にとって肝要なのは、世界を変えることだ」という文章がありましたね。ここにマルクスが理論活動に立ち向かった根本精神があるわけで、その意味でも、革命論を抜きにしてマルクスの学説は成り立たないと思います。
『資本論』を読むうえでも、マルクスが資本主義社会を革命のために研究したのだということを頭において読まないと、マルクスの本当の意味がつかめない。このことは、私自身、これまで以上に強く感じていることです。
石川 学者としてマルクスを研究する人たちの側にも、変革の運動論を学問的な検討対象として積極的にはとらえず、そこは政治家や政党にまかせるという傾向があったかもしれません。しかし、マルクスは、社会変革の実践を科学の対象としてとらえることを「新しい唯物論」の出発点としたわけで、そのことの意義をあらためて深く認識する必要があるわけですね。
実生活でも革命運動の比重は大きかった
不破 革命運動と経済学研究の関係では、エンゲルス自身、ある時期には、マルクスにあまり運動に力をそそがないで、『資本論』を早く完成しろと催促したこともあったのですね。しかし、そのエンゲルスが、マルクスの死後、彼がやっていた仕事を引き継いでみると、各国の革命運動への助言がどんなに大事な任務なのかということを痛感するのです。
マルクスの死んだ翌年(1884年)、マルクスを第一バイオリン、自分を第二バイオリンにたとえた有名な手紙がありますが、エンゲルスがそこで「マルクスを失ったことの重大性」をなによりも強調しているのは、革命運動でマルクスが発揮した眼力でした。
『資本論』第3部への「序言」では、自分の担う仕事のなかで、各国の運動上の要請にこたえる仕事を、「私のように50年以上もこの運動で活動してきた者」にとっては「いやおうなしの、ただちに果たすべき義務」なのだとまで書いていますし、94年12月にマルクスの次女、ラウラ・ラファルグにあてた手紙では、その任務に応えるという目的のために、自分はヨーロッパとアメリカの七つの日刊紙と19の週刊紙をとっている、と話しています。『資本論』第2部、第3部の編集という大仕事をかかえながら、革命運動のためには、こういう生活と活動を日常不断にしていたのですよ。
運動発展の節目にはつねに2人の助言があった
山口 エンゲルスが「序文」のなかで革命観の発展のあとをふりかえったことを、不破さんは、マルクスやエンゲルス自身の歴史的な自己検討だと特徴づけていますが、革命論が理論全体の要であるからこそ、これだけ深くえぐったのだという感じをあらためて受けました。
不破 実際、エンゲルスが描いた歴史は、外から観察したただの客観的な考察ではなく、路線を転換しその新しい道を進む節々のすべでが、マルクス、エンゲルスが直接タッチしてきた歴史だということも見逃せないことですね。
多数者革命の開拓者として、ドイツの党がはたした役割が指摘されていますが、そのドイツで、現実に議会が誕生する前から、近く生まれる運びになっている議会が、ドイツの党の活動にとって重要な国民的舞台となることを予見したのは、エンゲルスでした。その後の発展でも、またドイツの成功の経験をヨーロッパ諸国に広げる上でも、マルクスとエンゲルスはつねに大きな役割をはたしました。
マルクスがフランス労働党の指導部の要請を受けて、綱領の前文を執筆し、普通選挙権を欺(ぎ)瞞(まん)の道具から「解放の道具」に転化させるという方針を明記したことも、新しい路線をヨーロッパの運動に広げる上での重要な出来事でした。
このように、ヨーロッパの運動を多数者革命の方向に転換させる一歩一歩に、マルクスとエンゲルスがずっとタッチし続けてきたわけで、そのことがエンゲルスの文章に現実的な重みをもたせています。
石川 今まで抱いてきたマルクスやエンゲルスの像が、どこまで正確なものであったのか、そこが問い直されている気がします。哲学者としてあるいは経済学者として、マルクスやエンゲルスがどう理論的に成熟していったかという書き物は目にふれることも多いですし、あるいはマルクスたちのそういう側面だけを抜き出して読むという弱点が、自分の中にあったのかもしれません。私もこれまで、マルクスをひと言で言えば革命家ですと強調してきたわけですが、マルクスの理論の全体を「革命家マルクス」という角度から総体としてとらえる点では、まだまだ課題がありそうです。
マルクス研究の新しい地平が提起されている
石川 不破さんが指摘されたように、革命論の転換と経済学研究の転換が同時に起こったということだけではなくて―それ自体が重要な指摘であるのはもちろんですが―、革命論の転換が『資本論』の書き方の変化として現れているというところまで、両者の関係を突っ込んで理解することが必要なのですね。これは非常に大きな課題です。
山口 この本でも、『資本論』の形成史についての「マルクスの経済学研究と革命論展開の相互作用」という「注」があります(49~50ページ)。革命論の分野は科学的社会主義の理論史のなかでは落とされていた分野で、とくに多数者革命論は、スターリン流の「マルクス・レーニン主義」では完全に消えていきました。そういう意味で言うと、マルクスの学説について、不破さんの研究で新たに明らかにされてきた面が多くあって、経済学の分野でも、『資本論』の成り立ちの分野でも、新たな地平に立ってよく見ていく必要がある、そういう課題が提起されてきたのではないでしょうか。
石川 エンゲルスが主張して、日本共産党が引き継ぎ、発展させてきた多数者革命論には、社会の段階的な改革の前進に、その段階に応じた主権者としての国民の成熟、政治的教養の深まりや社会を制御する能力の成熟が対応するという論点がふくまれていますね。そういう社会の発展と個人の成長の関連については、日本社会の現状分析にもからめて、もっと突っ込んだ議論をする必要があるのかもしれません。
ドイツ革命への最後の助言。しかしドイツの党は…
不破 エンゲルスはこの「序文」の後半をドイツ革命論にあてています。
ドイツというのは、多数者革命の路線に立った運動で大きな前進をして、労働者党が議会で大きな勢力を持つようになった国です。イギリスやアメリカのように、議会制民主主義、あるいは人民主権の体制が確立している国であるなら、この道を前進すれば、合法的に権力を獲得する道が開かれるわけですが、ドイツはそういう国ではない。政府は皇帝が任命するものであって、権力問題では議会は無力なのです。
エンゲルスはこれまでの選挙の前進ぶりからいって、現実に多数を獲得する日も決して遠くはないと見ていましたが、そうなるといや応なしに政治的危機が起こって、最後にことを決するのは、それこそ強力と強力のぶつかりあいにならざるをえません。そういう条件を持った国で、多数者革命をいかにしてやりとげるか、エンゲルスはこのたいへんむずかしい応用問題に、「序文」後半で取り組んだのでした。
この問題は、社会主義者取締法という弾圧立法がなくなり、ドイツの党が合法性を回復し、新しい党綱領を採択した1891年のエルフルト党大会のさいにも、エンゲルスは、党指導部に手紙で真剣な検討を求めた問題でした。党勢力の増大とともに「決定的な瞬間」が迫ってくることは目に見えているのに、党は何の準備も討論もしていないではないか、こんな調子ではいざというときに党全体が“突然途方に暮れてしまう”ことになる、そんなことでいいのか、という実に痛切な警告でした。
それにも何の回答もないので、エンゲルスは、「序文」の後半をドイツの党への助言にあて、その「決定的な瞬間」に備えていま何をし、予想される相手側の攻撃をどのように迎えるべきか、暴発することなく相手を追いつめいかにして勝利の条件をつくってゆくか、そのための実に緻密な作戦方針を展開してみせたのでした。
山口 なるほど。この本の106ページにこういう文章があります。
「エンゲルスのこのような考察のあとをたどると、ドイツのような『議会の多数を得ての革命』路線が成り立つ政治体制的な条件がない国でも、少数者革命的な暴発をつねにいましめ、反動権力を人民の多数者で包囲し、政治的危機と『力の対決』の局面でも多数者革命の路線で勝利の条件を確保するために、彼がいかにその知恵と努力をつくしたかが、よく分かります」
今の話を聞いて、当時の事情とエンゲルスがこの文章にかけた痛切な思いがいっそうよくわかりました。
革命権をもっと知らせる必要がある
石川 エンゲルスがここで「革命権」の問題から始めているということが指摘されていますが、私は学生たちと接していて、これは今日的にも非常に重要な議論の立て方だと思います。一方で学生たちにとって「革命」は死語あるいは歴史的な用語になっています。それは遠い昔の動乱の時代のことであるといった理解です。同時にその「革命」は“反社会的な反乱”という印象で理解されてもいます。
しかし、少なくとも近代以降の人類社会では、不当な政治を打ち倒す革命は、主権者たる国民の権利ととらえられています。このそもそも論を国民主権の理念と結びつけて、ていねいに語ることが必要ですね。あわせて現代における革命がもはやいつでも「強力」と不可分なわけではなく、平和的に行われる可能性を広げていることについても強調する必要がありますね。
不破 最初の人権宣言と言われるアメリカの独立宣言(1776年)は、ものすごく強烈な言葉で革命権をうたっていますよね。
山口 革命権のところでは、日本の歴史をその目で見るということで、日本でも歴史的には革命の連続だったことをあきらかにしています。そのなかで、新しい支配者が自分の支配権を根拠づけるために、前代の権威を使ってきたというだらしなさの指摘があり、明治の天皇制政権の成立では、根拠を神話に求めざるを得なかったという指摘がありますね。エンゲルスのいう革命権の意味を日本の歴史のなかで考えさせる、このへんも『古典教室』のおもしろいところです。
二人は反動の時期にも運動とのきずなを離さなかった
石川 革命運動の具体的な指針を次々と提起していくエンゲルスの能力は、彼の生涯のどういう過程で培われていったのでしょう。そういう点に注目して勉強した記憶が私にはありません。やはり革命論への着目が希薄だったのですね。マルクスについては、48年の革命の前後やそこにいたるまでに集中的な実践や研究がありましたが、イギリスに亡命してからは経済学研究の比重がグッと大きくなり、インターナショナルができるまでは運動の指導からかなり離れていたというイメージもありますが。
不破 48年の革命以後はヨーロッパ全体で運動が沈滞期でしたから、表立った政治活動を展開する舞台はほとんどありませんでしたが、マルクスは、各国の革命家との手紙での交流もあるし、ドイツからは労働者の代表団が助言や意見を求めて何度もロンドンにやってくる、アメリカ、イギリス、ドイツ、オーストリアなど各国の新聞の寄稿家となって政治論説を発表する、そういう活動はずっと続けて革命運動、政治運動とのきずなをきったことはないのですよ。
ですから、インターナショナルができるときには彼は著名な革命家としての声価を得ていて、創立の大会にも招待され、この組織のなかですぐに頭角をあらわして事実上の指導者になってゆきます。そしてこの活動にはそれこそ全力投球で打ちこみました。
私が驚くのは、むしろエンゲルスの方です。インターナショナルの活動に参加するまでは、エンゲルスはマンチェスターで資本家仕事もやっていたわけですね。
山口 ええ、70年9月までやっていますね。
不破 マンチェスター時代にも、彼は昼は資本家の仕事をしながら、夜は革命的な文筆活動に取り組むという二重生活を20年間やってきたのですね。だから70年10月に運動の任務に着いたら、マルクスの片腕となってその任務を果たせるだけの用意をしていたわけですが、それにしても、マンチェスターからロンドンに移って、頭と仕事をパッと切り替えられるというのは、すごい能力だと思います。