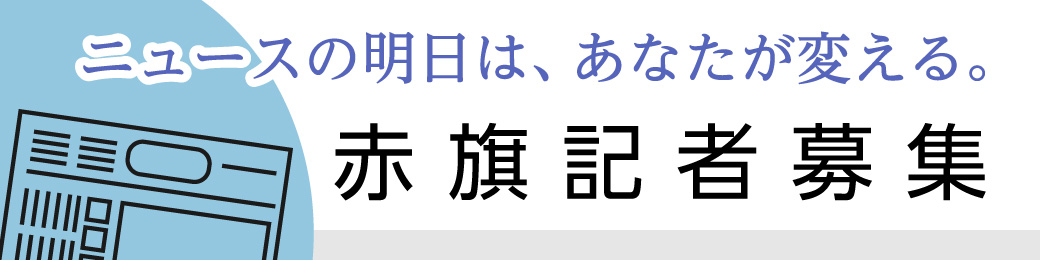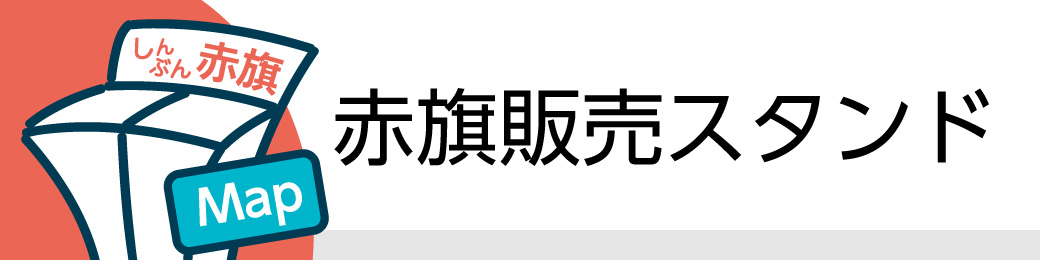2013年11月22日(金)
『古典教室』第2巻を語る
『空想から科学へ』――科学的社会主義の入門書
世界観から未来社会論まで 新たな光を当てる
『古典教室』第2巻はエンゲルス『空想から科学へ』に新たな光を当てました。講義を担当した不破哲三・党社会科学研究所所長と、石川康宏・神戸女学院大学教授、山口富男・党社会科学研究所副所長の3人が第1巻にひきつづいて語りあいました。
 (写真)新日本出版社1400円 |
―『古典教室』第2巻はエンゲルス『空想から科学へ』(1880年)が中心的なテキストです。
山口 『空想から科学へ』は、科学的社会主義の理論を学ぶのに最も利用されている古典ですが、今回の不破さんの講義には、新しい探究が多くあって、この理論の成立の歴史を考える上でも、世界観から未来社会論にいたるまで、新しい形での入門の著作となったのではないでしょうか。
第1章 空想的社会主義とフランス革命
「空想」から「科学」への飛躍
不破 最初にいっておきたいのは、この本が「科学的社会主義」という言葉が市民権をはっきり得た本だということです。マルクスはそれまで自分の理論に特定の名称をつけることはしなかったのですが、『資本論』第1部(1867年)を出した頃からエンゲルスがそういう意義づけをしはじめました。そしてこの本の序文で、マルクス自身も、これを「科学的社会主義の入門書」だと書いたわけで、この点でも、科学的社会主義の成立の歴史のなかで、面白い位置にあるのですね。
石川 空想的社会主義から科学的社会主義への飛躍の大きさを実感する上で、第一章は大切だと改めて感じさせられました。空想的社会主義は、理論の形式の面でフランス革命当時の啓蒙(けいもう)思想と変わらないところがあり、科学的社会主義はその形式をひっくり返すものになっている。そのような角度から科学的社会主義の理論史上の位置づけが与えられていますね。
不破 空想的社会主義の理論的形式が啓蒙思想家たちと同じだ、こういう角度からの批判は、エンゲルスの独自の着想だと思いますが、これで石川さんのいう「飛躍」の意義がくっきりわかるようになりました。
フランス革命史の「政治講談」
 (写真)(左から)党社会科学研究所副所長 山口富男さん、党社会科学研究所所長 不破哲三さん、神戸女学院大学教授 石川康宏さん |
不破 ただ、ここのところは、フランス革命の歴史がわからないと、エンゲルスのいう意味が良くくみとれないのです。そこで私もあらためてフランス革命の歴史を勉強しなおしたのですが、取り組んでみてこの革命のなかで働いた法則的発展がつかめてくる感じがしました。それで、エンゲルスが論じてない部分まで含めて革命史を話すことにしたのです。これは、第4課でやる革命論にも役立ちますから。
山口 不破さんは革命史の部分は“政治講談”と思って気軽に聞いてほしいと言いましたが、ここは読んでいて面白いのですね。1789年から94年までの革命史を四つの段階に分けて、その時期ごとの特徴、民衆の決起とそれで革命が進むことなどが、生き生きと語られています。これからマルクスなどの古典を読む時にすごく力になる「政治講談」でしたよ。
石川 革命の一つ一つの段階で、次の段階に進もうとする力が社会のどこにあったかが描かれており、それによって革命が偶然のことではなく、封建的な社会から資本主義の社会への前進が、一直線に現れるわけではないけれど、誰にも押しとどめられないものとして貫かれる。そういう経過がリアルにわかるものになっていますね。
多数者革命論は長く歴史に埋もれていた
石川 このフランス革命のあり方はマルクスにも強く影響して、それを乗り越えて労働者階級の革命の理論を発展
 (写真)不破さん |
不破 フランス革命型の革命観は、19世紀のヨーロッパで圧倒的な影響力をもちましたからね。革命家はみんな、革命はあのように進むものだと考えていたのです。これは、20世紀にまで響いていて、ドイツ社会民主党の左派として活動した有名な女性革命家のローザ・ルクセンブルクは、1905年にロシア革命が起きた時に書いた論文で、革命というものは自然発生的に起きるもので、革命を党が準備したりするのは邪道だと論じました。
マルクス、エンゲルスは、フランス革命型の革命観からぬけだして多数者革命論を発展させ、エンゲルスは、ドイツのような専制国家で多数者革命を進める戦術を党に勧告する論文まで書いたのですが、それがほとんどドイツの党の左派にも引き継がれなかったのです。この点は、レーニンにも本格的な研究はありません。長く科学的社会主義のうずもれた歴史の一つとなっていました。
第2章 科学的な世界観と弁証法
なぜ弁証法からはじまるか
―『空想から科学へ』の第二章は、世界観全体を解説するところですね。
石川 ここでは弁証法の解説からはじめて、唯物論、史的唯物論と進んでいます。これは、マルクス、エンゲルスの頭のなかで学問が成立していった筋道をなぞったのでは、との説明ですが、なるほどそうかと思いました。教科書類では唯物論から始めるのが普通ですが、そうするとそれぞれの要素が縦割りに区切られ、相互の関係が説明しづらくなるところがあります。それがここではひとつの太い流れをつくっていますね。
不破 マルクスを読んでいると、哲学的に唯物論か観念論かで悩んだ形跡がほとんどないのです。それは、この時代に一番大きな力を持ち、マルクスが乗り越えなければならなかった相手が、いわゆる客観的観念論者のヘーゲルだったという時代状況が背景にあると思います。ヘーゲルの場合、世界を支配する「絶対者」「絶対理念」はあるのですが、事物の世界と人間の認識の関係といった問題では、唯物論者とあまり区別のない議論を展開するのです。だから、マルクス、エンゲルスがぶつかった問題は、ヘーゲルの逆立ちした弁証法や理念中心の社会観を唯物論でひっくり返すことにあったのでした。
レーニンの時代になると、新カント派などが20世紀初頭の自然科学の危機と結びついて、哲学界で優勢になっただけでなく、自然科学者まで影響を受けましたから、レーニンは、唯物論か観念論かの問題を中心において、『唯物論と経験批判論』という力作を書きました。
しかし観念論は、自然科学が発展すると足場がなくなります。現代では、生命や人間の意識の問題まで、自然科学的な解明が進みつつある時代ですから、時代状況としては、唯物論か観念論かの勝負がついたという感じがします。
党活動のなかの弁証法
 (写真)石川さん |
石川 弁証法の説明で、形而上学の石頭的な見方と弁証法的な見方を、三つの点から説明されていますが、その三つの関係をみると、一つ目の連関の問題と二つ目の発展の問題を、より突っ込んで語ったものが三つ目の対立・矛盾の問題となっているように思いますが。
不破 もちろん、互いに関連はあるのですが、三つ目の対立・矛盾を抜きにすると、連関も運動も生きた形ではとらえられないという問題があるのではないでしょうか。だからエンゲルスはその点を一生懸命説明している。エンゲルスが、矛盾・対立があらゆる運動の原動力だという式の“矛盾論”ではなく、「固定された境界線はない」という言葉に代表される、ものごとをとらえる上での認識と概念の柔軟性を強調している点は、とくに注意して読むべき点だと思います。
石川 つづく「党活動のなかでの弁証法」は、大胆な切りこみですね。
山口 この話の時には、教室の雰囲気は、弁証法を語ってこれほど笑いが起こったことはなかったのではないかと思うほどです。たとえば、「量から質への転化」の話のところで、党活動では「果報は寝て待て」はないのだと話した時などは、爆笑でした。
不破 弁証法というものは、学問的な研究の方法であるだけでなく、日常の活動のなかでも大事な、ものの見方の根本にかかわるものですから、そういう応用問題として取り組んでみたのです。私としても、初めてやったことですから、どれだけ成功しているかは、講義を聞いたみなさんの意見を聞かないとわかりませんね。
山口 今度の「古典教室」は綱領的、世界観的な確信をつかもうということで出発しています。それには、一人ひとりが自分のものの見方、考え方を、もう一度吟味しないといけない。講義のなかで、選挙で負けてもそこにどんな前進の芽があるかつかむなど党活動そのものが弁証法の事例の宝庫だと語られました。
日頃の生活や活動の中で自ら考える材料を提供したものとして連続教室らしいですね。
石川 哲学は、出来上がったお題目を覚える学問ではなく、現実の世界に貫く法則を見つけだす方法や一般的な成果を示すものだと理解してもらう上で、わかりやすいものになっていると思います。
現実と格闘するなかで弁証法を生かす
不破 弁証法というのは、特徴や定式を覚えたら、それで万事済むかというと、そうではないのですね。弁証法が生きるには、対象と本当に取り組んでいわば現実と格闘しながら、その中で初めて弁証法の柔軟な考え方が生きてくる、こういう関係が大事だと思います。
マルクスだって、『資本論』の草稿を書きはじめるとき、「社会の変革は、生産力の発展が古い生産関係と衝突するときに起きる」という弁証法を根本にもって、その目で資本主義社会を研究しようとしました。しかし、そういう方法論、観点を持ったから、その矛盾の現れ方がすぐつかめるかというと、そうではなく、『資本論』第1部にその研究が実るまで、それこそ言葉に尽くしがたい苦労をほぼ10年間にわたってしたのです。
マルクスが自分の弁証法を特徴づけた言葉に、「素材の中をのびのびと動く」という言葉があります。対象を徹底した研究で本当に自分のものにし、そのなかで働いている法則を見つけ出し、そのことを後でふりかえってみると、ああこれが弁証法だなと気づくようなことが何度もあったのだと思います。
第3章 資本主義社会の特徴。変革の必然性
―『空想から科学へ』の第三章は、「古典教室」では、前半の資本主義論と後半の社会主義論との2回に分けて、それぞれ、エンゲルスの本文の説明に対応するマルクスのテキストをあわせて読むという講義でした。まず資本主義の分析から。
エンゲルスの基本矛盾論の誤り
石川 資本主義論の部分の核心は、資本主義の基本矛盾をめぐっての、エンゲルスとマルクスのとらえ方の違いですね。この違いについては、経済学者の間にも以前からいくつかの議論がありました。そこを不破さんが、もう10年くらいになりますか、ずっと研究されてきた。僕も、矛盾のとらえ方としてマルクスの方が現実の変化をとらえる生きた力をもっており、エンゲルスの方が静的だと思ってきましたが、両者の違いをはっきりとらえるには至りませんでした。
その点、不破さんのこの本での指摘は非常に明快ですね。マルクスにもエンゲルスにもいいところがあるといった話ではなく、エンゲルスの基本矛盾論の弱点が生産関係のとらえ方にあるということを明快に指摘されている。ここは衝撃的な思いをもって読んだところでした。
 (写真)山口さん |
山口 問題の全体が見えるように論じられたのは、今回が初めてですね。エンゲルスがなぜそういうとらえ方になったのか、エンゲルスの考察の経過をきちんとおさえ、それと対比しながらマルクスの資本主義の矛盾のとらえ方を論じてゆく。そこにマルクスのとらえ方は、現代の日本や世界の経済的な諸矛盾をとらえる上でも力を持っているという証明が入ってきます。
不破 私自身、マルクスやエンゲルスの経済学を勉強した最初から、「生産の社会的性格と取得の資本主義的性格の矛盾」というエンゲルスのとらえ方は当然の「鉄則」のように受け取ってきました。だから、これはおかしいのではと思いだしてからも、間違いだと言いきるまでには時間もかかったし、研究も重ねました。
この命題をエンゲルスがどこから引き出してきたのか、その経緯をたどってゆくと、生産が社会的になったのに取得形態は資本主義以前、小経営の時代の古い形態をそのまま引き継いでいるという矛盾のとらえ方にありました。エンゲルスは生産関係を取得形態の角度からとらえて、それが小経営の延長だと見るのですから、最初から資本家による労働者の搾取を外したところで、資本主義の生産関係を規定づけてしまったのですね。そこにエンゲルスの“我流”があるのだと腑(ふ)に落ちて、彼の定式そのものを根本から検討するところへ進んだのです。
矛盾の根源は「利潤第一主義」にある(マルクス)
不破 マルクスは基本矛盾という言葉を使いませんが、資本主義の本来の限界とか、資本主義の矛盾とかをいう時には、必ず、資本主義が労働者のより大きい搾取、より大きい剰余価値の追求を最大の推進力にしていることを指摘します。いま私たちが使っている言葉でいえば、「利潤第一主義」にこそ、資本主義のあらゆる矛盾と限界、危機の根源がある、ということです。
石川 しかし、社会主義が科学になるためには、史的唯物論と剰余価値論が必要だったと書いたエンゲルスが、資本主義の基本矛盾の定式化にあたって剰余価値論を入れられなかったのは、どうしてなのでしょうね。
山口 それは『空想から科学へ』の謎でしたね。
不破 エンゲルスの“我流”には歴史があって、彼は、1844~45年に書いた経済学の論文「国民経済学批判大綱」や著作『イギリスにおける労働者階級の状態』などで、労働者の貧困から恐慌まで、資本主義のすべての害悪の根源は「競争」にあると論じていました。マルクスが剰余価値を発見した後も、「競争」=悪の根源論を引きずっている印象があります。『空想から科学へ』でも、「無政府性」に諸悪の根源を求める議論があちこちで顔をだしています。
それから、歴史的制約という問題もあります。私たちは資本主義を論じるとき、『資本論』全3部を必ず頭に置きます。しかし、マルクスは『資本論』の草稿をエンゲルスにも見せませんでしたから、エンゲルスが『空想から科学へ』を書いたときには、『資本論』の第2部、第3部でマルクスが何をどう論じているかはまったく知りませんでした。だから、経済学に関して言うと、エンゲルスの思い違いという部分があっても不思議ではないのですよ。
石川 たしかにエンゲルスは、資本主義の害悪を生産の無政府状態に還元する傾向が強いですね。生産の無政府性こそが、あらゆる害悪を生み出す推進力だというとらえ方です。しかし無政府性は商品経済一般の特徴であって、それでは資本主義の経済が新しく生み出した問題を把握したものにはなっていないのですね。
不破 恐慌にしても、根底には商品経済の無政府性があります。だからマルクスは、商品経済のなかに恐慌の可能性があることをまず指摘します。しかし、そこで話が終わらないで、この可能性が現実性に発展するには、商品経済一般の段階ではまったく存在しない諸条件、諸関係が必要になるという注釈をきちんと書き、その諸条件の探究へと研究を進めてゆきました。
ところが、エンゲルスの論だてでは、無政府性から恐慌が生まれるといって、分析がそこで終わってしまうのです。恐慌でも、そこから大きな違いが出てくるのですね。
マルクスも最初から完成した恐慌論を持っていたわけではなかったことは、前回の鼎談(ていだん)で話したことでした。
石川 こういう具合に資本主義論が深められているのは、マルクスをマルクス自身の歴史の中で読むという研究の大きな成果ですね。基本矛盾論、恐慌論、恐慌論と革命論のつながりなど、科学的社会主義のとらえ方全体が揺さぶられるような、大きな問題提起が重ねられていると思います。
第4章 社会主義社会とその展望
「自由な生産者の連合」という体制をどうつくるか
山口 『空想から科学へ』の第三章の後半には、生産手段の社会化、国家の役割と死滅にかかわる問題などがぎっしり詰め込められています。
不破 エンゲルスは短い文章で社会主義の全体像を要領よく説明してあるのですが、私たちがスターリン以来のソ連の変質と崩壊を経験した今、その経験に立ってマルクスの未来社会論をつかもうと思うと、それに必要な部分で説明が飛んでいると思う部分がかなりあるのです。今度の講義で、エンゲルスの本文を説明した後で、マルクスの一連の文章をテキストにくわえて補足的な話をした一番大きな理由はそこにありました。
山口 説明が飛んでいるというのは、どの点ですか。
不破 一つは、「過渡期」の話が飛んで、「国有化」からすぐ「国家の死滅」の話に移ってしまうところですね。
マルクスも『共産党宣言』ではこういう言い方ですませていますが、その後、そこをもっと深く考えるようになったのです。
簡単にいうと、生産手段が社会の手に移っただけで、はたして「自由な生産者が連合した社会」になるだろうか、という問題です。
マルクスがこの研究に本格的に取り組んだのは、1871年、パリ・コミューンの時期でした。パリの労働者の壮挙を目の前にして、社会変革の前途に考察をめぐらせたのですね。マルクスが到達した結論はこうでした。
――生産手段の持ち主が資本家から社会(たとえば国家)に代わっても、資本主義時代に生産の体制にしみついた“奴隷制のかせ”がなくならなければ、自由な生産者の連合とはいえないし、社会主義の社会の経済的土台もできない。(「フランスにおける内乱」第1草稿から)
マルクスがここで、“奴隷制のかせ”という言葉で指しているのは、資本主義の工場で支配的な、資本家やその代理人が工場の支配者として労働者を指揮・監督する生産体制のことです。この上下の体制がそのまま残ったのでは、労働者が本当に解放されたとはいえない、労働者が自発的に結合し自覚的な規律をもって共同して働く新しい体制を作り上げよう、という問題です。
権力をとって国有化するのは短い時間でできます。しかし、自由な労働者の連合といえる新しい生産の組織をつくりあげるには、時間がかかります。しかし、これをやり遂げないと、社会主義への移行が完了したとはいえないわけで、そこから、マルクスはこの時期を「過渡期」と呼ぶようになったのでした。
私たちは、このことを、「生産者が主役」という言葉で、党の綱領に書き込みました。
ソ連の経験はマルクスの予見を実証した
山口 パリ・コミューンを研究しながら、その事業の前途をそこまで見通したのは、すごいことですね。
不破 この時点では、マルクスの予見でしたが、その指摘の重要性を実証したのがソ連の経験でした。ソ連では工業の国有化は全面的に実行されました。しかし、その国有化企業のもとで、“奴隷制のかせ”は資本主義以上の過酷さで生き続けました。「集団化」という形態で「社会主義化」されたといわれた農業でも、“奴隷制のかせ”のひどさは工業部門以上のものがありました。「国有化」の形だけでは新しい社会はできない、生産者が主役という体制をそこに築いてこそ、新しい社会の土台ができる。まさにこのことが実証されたのでした。
山口 「社会主義をめざす国」でも、この問題を本当に追求する試みは、まだやられていないのが、現在の世界的な到達だといえますね。
石川 マルクスがその過渡期論をのべた文章には、「この刷新の仕事が、既得権益と階級的利己心の諸抵抗によって再三再四押しとどめられ、阻止されるであろう」という言葉がありますね。不破さんは、ここの「抵抗」を、かつての資本家階級によるものではなく、労働者の中にある既得権益や利己心から生まれるものだと解説されています。これはどういうことを念頭にしてのことなのでしょう。
不破 たとえば生産の指揮者になった幹部が、支配者的にふるまうことも予想されうることです。現場の各級の監督者などが民主的な生産体制に抵抗することもあるでしょうし、普通の労働者のあいだにも、「主役」になって生産全体への集団的責任を負うことなどいやだといって新体制にそっぽを向くものも出るかもしれない。さらに生産物の社会的な管理の分野では、もっと複雑で重大な問題も起こりえます。マルクスは、この言葉をかなり広い意味で使っていると思います。
社会発展の推進力が「自由の国」に移る
山口 『古典教室(第2巻)』の最後は、『資本論』第3部にあるマルクスの未来社会論です。マルクスは未来社会を考えるときに、労働時間の短縮が人間の自由な共同体をつくっていくうえで大事な核になるといっていますね。
不破 私が、『空想から科学へ』の説明で「飛んでいる」点があるといった二つ目は、この問題でした。
労働、つまり生産活動は社会の土台ですが、そこの変化だけで社会を見ると未来社会の本当の姿は見えてきません。
レーニンの『国家と革命』での未来社会2段階論の一番の問題は、生産物の生産と分配がすべてという立場で未来社会をとらえていることでした。だから、生産力が発展して社会が豊かになり、誰でも「必要に応じて」消費できる社会になることが、共産主義の一番高度な段階だということにもなります。
しかし、マルクスが描いた未来社会像の中心は、「人間の発達」が保障される社会です。社会が変革されて、社会が必要とする生産労働をみんなで分担するようになったら、一人ひとりの労働時間が短縮されて、自由に使える生活時間が大きくなる。マルクスは、この自由な時間を「自由の国」と呼びました。
未来社会では、人間の力を自由に発達させる条件が、社会のすべての人に保障される。これは、人類社会が歴史上かつてない発展の能力を持つということです。そこで科学技術が発展し、それが経済に生かされて労働の生産性が高まれば、その成果をうけて労働時間がさらに短縮され、「自由の国」はさらに領域を広げる。未来社会では、こういう循環が働きだします。
資本主義社会では、利潤第一主義が経済発展の最大の推進力ですが、未来社会では、「自由の国」での「人間の能力の発達」が社会発展の最大の推進力になってゆくでしょう。
マルクスが『賃金、価格および利潤』で述べた言葉―「時間は人間発達の場だ」ということを正面にすえて未来社会の全体像をとらえることが大事なんです。
従来の社会主義論というのは、たいていが生産物の分配どまりで、経済的土台の変化だけに目を向けて、人間の発達という肝心のことが出てこないというところに大きな弱点がありました。
この見地をきちんと根本にすえないと、社会主義がなぜ人類発展の時代になるのか、人類社会の「本史」のはじまりといえるかが、説明できないのですね。エンゲルスは、人類社会の飛躍的発展の時代となる未来社会の姿をいろいろな面から強調していますが、なぜそうなるかの根拠の解明に弱点を残していると思います。
山口 不破さんは、「人間の能力の発達」を中心に据えたマルクスの未来社会像が「早い時期から長い時間をかけて熟してきた」と書いていますが、それは、マルクスが「人間の解放」の問題でヘーゲルを乗り越えて行く若い時期からの出発になっているのでしょうか。
不破 「人間の解放」というのはマルクスが早くから持っていた問題意識ですが、それが「人間能力の発達」ということに絞られてくるのは、少し後になりますね。『ドイツ・イデオロギー』(1845年)の段階は、例の「朝は狩りをし…」という調子でしたからね。文献的な証拠で、「人間の発達」が未来社会の中心問題になってくるのは、『資本論』にいたる最初の草稿、『57~58年草稿』だと思います。
山口 『古典教室』は「わが党は、こういうことも綱領の未来社会論の柱にすえ、社会主義の大きな展望を明らかにした」と結ばれています。その意味が確認できると思います。
―今日はどうもありがとうございました。
(第2巻 おわり)
(第1巻は10月11日付に 掲載しました)