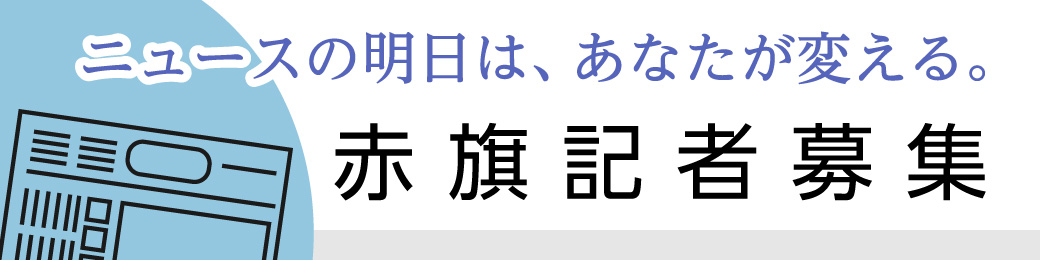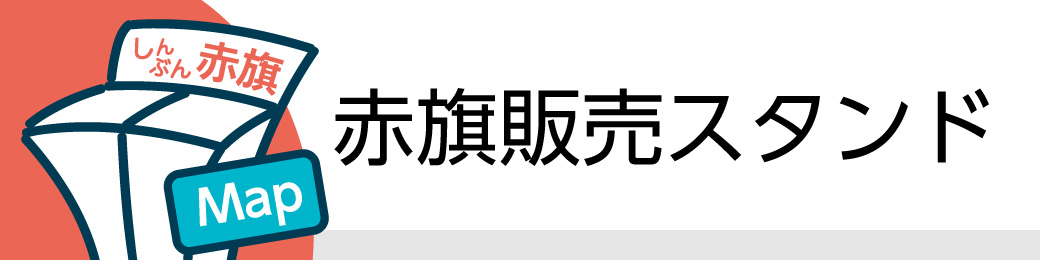2012年11月23日(金)
きょうの潮流
題して、「そのとき画家は何を見つめていたのか」。東京・世田谷美術館で始まった、「松本竣介展」のうたい文句です▼36歳の若さで病死し、ことしが生誕100年にあたる松本竣介。会場で、やはり1942年の「立てる像」が目をひきます。黒い作業着風の上下のつなぎを着る彼自身が、さびしい道の上にひとり立つ。まるで巨人のように▼無表情にもみえる顔つき。まっすぐな視線。なるほど、「そのとき画家は何を見つめていたのか」です。「立てる像」は、戦争一色の時流になびかず自分の絵を描き続けた、竣介の生き方をしめす代表作とみなされてきました▼「議事堂のある風景」にも興味を覚えます。青みがかった暗い色調。右側の奥に、国会議事堂が廃虚のようにたたずむ。1942年1月の作です。前年の12月に太平洋戦争が始まったばかりのとき、画家は国会議事堂をのぞむ場所で何を見つめていたのでしょう▼何を見つめていたのか、展示中の手紙や発表文でいくらかうかがい知れます。戦争責任を問う、戦後の彼の筆は手きびしい。「出版界の戦犯追窮も始まっているが、…日本の新聞社等は全部解散になるのが当然だ」とさえ、いいきりました▼美術家の組合の結成をよびかける文には、政治家・尾崎行雄の言葉を引いています。「政党というものは主義方針によって、離合集散しなければならぬが、日本では親分子分の主従関係という頭でやっている。これは政党ではない徒党である」。時節柄、考えさせられました。