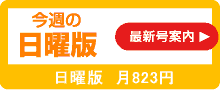2006年12月18日(月)「しんぶん赤旗」
再開6カ国協議
政府に求められる対応は
北朝鮮の核問題をめぐる六カ国協議が十八日から北京で再開されます。日本政府は北朝鮮のすべての核兵器と既存の核計画の放棄に向け「早期の具体的な成果を求め」(安倍晋三首相)るとともに、日本人拉致問題も取り上げ、「早期解決の重要性を訴えていく」(同)方針です。
査察を主張へ
六カ国協議で米国は、(1)寧辺の実験用黒鉛減速炉と関連核施設の即時稼働停止(2)国際原子力機関(IAEA)の査察受け入れ(3)豊渓里にある核実験場の閉鎖(4)すべての核施設・核計画の申告―などの措置を求めています。日本政府は、米国と共同歩調を取り、その実現を図っていく考えです。
麻生太郎外相は、特に「核施設を放棄した、もしくは止めたという保証を取れる方法がIAEA以外にあるのか」(十二日の記者会見)と述べ、IAEAの査察受け入れを重視する考えを示しています。
一方で麻生外相は、現時点で北朝鮮以外の五カ国で一致しているのは(1)朝鮮半島の非核化(2)北朝鮮を核保有国と認めない―という範囲にとどまっているとの認識を示しています(十三日の衆院予算委員会)。政府は、六カ国協議での「具体的な成果」をめぐる認識の一致が図れるよう、米国などとともに議長国・中国に働きかける方針です。
拉致の問題も
拉致問題では、核放棄に向けた措置を具体化するために設置が検討されている「作業部会」の中で主張していく方針です。具体的には、「核廃棄・検証」「エネルギー支援」などに加え、日朝国交正常化に関する作業部会の設置が検討されており、その場で討議したい考えです。
しかし、北朝鮮側は「六カ国協議は拉致問題を取り上げる場ではない」などと繰り返し、反発しています。
これまでの六カ国協議では全体会合と並行して、日朝間の二国間協議も行われました。今回も実現するかが注目されます。
外交的解決を
北朝鮮のミサイル発射や核実験を受け、日本では、「敵基地攻撃能力」の保有や核武装論、「周辺事態法」発動などの軍事対応論が相次ぎました。しかし、米国も含め平和的・外交的な解決が国際社会の一致した流れとなり、日本国内の一部の強硬論は通用しなくなりました。
日本政府も「粘り強く外交的に努力を重ねていくのが第一にやること」(塩崎恭久官房長官、十一日の記者会見)としています。十一月に来日したIAEAのエルバラダイ事務局長は「日本は唯一の被爆国であり、広島や長崎に大変な被害を受けた。日本は核の倫理を語る責任がある」と述べています。
六カ国協議では、被爆国としての道理ある対応が求められています。