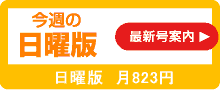2006年2月5日(日)「しんぶん赤旗」
米国防計画見直し
米英モデルに日米同盟強化
米国防総省が三日に公表した「四年ごとの国防計画見直し」(QDR)は、現在、日米両政府が進めている在日米軍再編の狙いを裏書きするものになっています。
■ともに血を流す
QDRは「この報告で提示されているビジョン(未来像)の達成は、米国の永続的な同盟関係を維持し、改造することによってのみ可能である」と強調。NATO(北大西洋条約機構)やオーストラリア、韓国とともに、日本との同盟関係を特別に挙げて、「軍事的な安全保障上の負担分担を促進する」よう求めています。
とりわけ、イラクやアフガニスタンで米国と共同して軍事作戦を展開している英国とオーストラリアを高く評価。「こうした密接な軍事的関係は、米国が他の同盟国や友好国と促進しようとしている協力の広がりと深さのモデルだ」と述べています。日本との同盟関係も、「米英同盟」や「米豪同盟」のように、米国の先制攻撃の戦争で“ともにたたかい、ともに血を流す同盟”へと強化する方針です。
そのために、同盟軍との「合同作戦」や「防衛システムのいっそうの統合」、「(米軍による)受け入れ国の基地の使用」などを重視。日本の自衛隊をはじめとする同盟軍との軍事一体化・融合の方向を強く打ち出しています。
また、米核戦略の一環に位置付けている「ミサイル防衛」では、「国際的な協力拡大」の「成功」例として、米国と日本が新しい迎撃ミサイルの共同開発で合意したことを評価。日本にいっそうの協力を促しています。
■非正規戦の重視も
QDRは、日米両政府が昨年十月に合意した在日米軍再編計画、とりわけ(1)米陸軍キャンプ座間(神奈川県)への新しい陸軍司令部(UEX)の創設(2)沖縄の米海兵隊部隊の再編(3)米空母打撃群の日本への長期的な展開―の意味も浮かび上がらせています。
米陸軍は現在、地球規模の先制攻撃作戦を実行するための組織「変革」を進めており、キャンプ座間の新司令部創設もその一部です。
QDRは、イラク戦争のような大規模な戦闘に加え、「変革」された陸軍や海兵隊による「特殊作戦」、対テロ・ゲリラ戦といった「非正規戦」の重視も打ち出しました。沖縄に駐留する陸軍第一特殊部隊群第一大隊(グリーンベレー)などの強化も考えられます。
在日米軍再編の日米合意では、沖縄の海兵隊について「緊急事態への迅速な展開能力を維持する」と強調しています。その主力である31MEU(第三一海兵遠征隊)は、QDRが打ち出している地球規模の迅速な展開能力、特殊作戦能力を兼ね備えており、いっそうの強化が狙われています。
■長期に前方展開
QDRはまた、十一個の空母打撃群のうち少なくとも六個を太平洋地域に配備するとしました。在日米軍再編の日米合意では、空母の「長期にわたる前方展開能力を維持する」ため、米海軍厚木基地(神奈川県)に駐留する空母艦載機部隊の米海兵隊岩国基地(山口県)への移転を計画。二〇〇八年には、米海軍横須賀基地(神奈川県)に、通常型空母に代えて原子力空母の配備を狙っています。
太平洋地域の空母六隻態勢に伴い、米海軍佐世保基地(長崎県)が準母港としていっそう重視される可能性もあります。
これらの動きも、QDRに示された太平洋地域の海軍戦力強化の一環です。(榎本好孝、竹下岳)
■日本に言及した部分(要旨)
米国防総省が三日に発表したQDRのうち、日本に言及した部分(要旨)を紹介します。
同盟国は明らかに米国の力の源泉の一つである。過去四年間、NATO(北大西洋条約機構)諸国やオーストラリア、日本、韓国などは国際安全保障への新しい脅威に対する新しい活力と適応性を採用してきた。米国は英豪両国と特別な関係を築き、イラクやアフガニスタンでの作戦などをともにたたかってきた。これらの緊密な軍事関係は、米国が他の同盟国や友好国にも求めているモデルになっている。
日米同盟はアジア太平洋地域の安定にとって重要である。
米国は、国際的な「ミサイル防衛」協力でも成功しつつある。例えば、日米両国は最近、海上発射型の次世代SM3迎撃ミサイルの共同開発で合意した。
米国の同盟国は、共通の安全保障問題に取り組む上での土台になっている。太平洋において、日本、オーストラリア、韓国などとの同盟関係は、地域における二国間および多国間の対処を促進している。