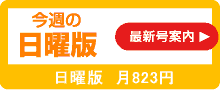2006年12月18日(月)「しんぶん赤旗」
マスメディア時評
世論に向き合い報じたか
安倍内閣が最優先の課題だとしてきた教育基本法の改悪が、自民・公明の賛成で成立しました。何のために改定するのか説明責任を果たさず、国家のための人づくりを進めた戦前の教育に逆戻りかという国民の疑念も踏みにじって、しゃにむに成立を急いだ政府・与党の責任は重大です。
新聞・テレビなどマスメディアも、大きなスペースを割いてこの問題を伝えてきました。しかし、ほんとうに問題点を伝えたか、国民の声に向き合って報じたか、その中身には問題を残したといわなければなりません。
各紙社説は二分
改悪が成立したのを受けた十六日付の全国紙の社説で見て、その立場は二分されています。
「教育と防衛 『戦後』がまた変わった」と論じた「朝日」や、「これで『幕』にしてはいけない」と論じた「毎日」のように改定に批判的な論調と、「さらなる国民論議の契機に」という「読売」や「改正教育基本法をどう受け止めるか」という「日経」、さらには「『脱戦後』へ大きな一歩だ」と前のめりに評価する「産経」など、改定に好意的あるいは推進する論調です。「東京」は「行く先は未来か過去か」と、全国紙より批判が強い論調です。
全国紙の二つの流れはちょうど一カ月前、衆院の委員会で改悪案が自民、公明の与党の単独で強行採決された際、十一月十六日付の社説でも同じでした。「この採決は禍根を残す」が「朝日」、「教育の『百年の大計』が泣く」が「毎日」で、「読売」は「野党の反対理由はこじつけだ」、「産経」は「やむをえぬ与党単独可決」と、明白に二分されていました。
問題は二分されて見えるこうした全国紙の論調が、国民世論の構成を反映しているのかです。
教育基本法改悪問題をめぐる国民世論で顕著なのは、改定の必要性についての議論は分かれても、圧倒的多数は、この国会で強行すべきではないということです。とりわけ「いじめ」自殺や高校での未履修、タウンミーティングでの「やらせ」や「さくら」の問題が相次いで持ち出される中で、改定を進める政府・与党の主張は急速に色あせ、何のために改定するのかの疑問は最後まで解消されませんでした。
全国紙の論調のうち、改定に批判的な「朝日」や「毎日」は、多かれ少なかれ、こうした国民世論を反映しています。しかし、改定を支持する「読売」や「産経」の立場は国民世論を反映したものとはとてもいえません。
とりわけ成立が強行された改定教基法を、「新しい日本の教育の幕開け」(「読売」)だの、「『戦後体制からの脱却』への大きな一歩」(「産経」)だのと最大限持ち上げてみせる推進派の論調は国民の常識からかけ離れています。何のための改定なのかが問われているときに、その疑問には答えずに持ち上げるだけでは、まさに国民を誤導するものというほかありません。
憲法と矛盾する
もちろん、改定に批判的な全国紙を含めて、報道の内容で見れば、何のための改定かなど問題の核心に迫り、浮き彫りにする点では不十分です。法案が成立した後では大きく取り上げるが、その過程ではいついつ採決されそうだといった“落としどころ”報道に終始し、問題の核心についてはまともに報道しないという傾向が根強くあります。こうした弱点は、いいかげんに克服すべきではないでしょうか。
とりわけ問われるのは、国の基本法である憲法に照らしてこの改定は許されるのか、核心中の核心ともいえる問題で、突っ込んだ報道や論評は数えるほどしかなかったことです。
たとえば、全国の弁護士が参加する日本弁護士連合会(日弁連)は、教育基本法は憲法に密接に関連した教育法体系の基本理念を定めた法律であると、その「立憲主義的性格」を強調して、改悪に反対してきました。その指摘を正面から受け止めた全国紙の論調は果たしてあったのか。
審議のなかでは、改定案は自民党の新憲法草案の精神と一致するという驚くべき文部科学相の答弁もありました。自衛隊を軍隊と認め、権力を縛るべき憲法で逆に国民を縛り付けようとする自民党新憲法草案と現行憲法は根本的に矛盾します。マスメディアがこうしたことを踏まえ、文字通り違憲の立法と言うべき改定案に立ち向かえば、その論調もずいぶん違ったものとなったに違いありません。
反対の運動や声に十分スペースを割かないというマスメディアの欠陥も相変わらずです。マスメディアとりわけ新聞には、読者・国民の声とより正面から向き合うことこそ求められます。(宮坂一男)