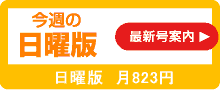2005年3月16日(水)「しんぶん赤旗」
アメリカ女性研究者の地位
ハーバード大学
学長の性差別発言
自然科学の研究者に女性が少ないのは社会的な偏見などとともに「本来備わった男女の差異」、つまり女性は生まれながらに科学が苦手だからだといった米ハーバード大のラリー・サマーズ学長の発言(一月十四日)が性差別発言だと波紋を広げています。
昨年十一月に東北大学で開催された「国際シンポジウム『ジェンダー法学・政治学の比較的展望』」でマサチューセッツ大学名誉教授マーティンさんの報告を思いだしました。
マーティンさんは、アメリカの語学、文学などでは博士号取得者の半数以上が女性なのに対して、数学、物理化学などでは新規に取得した八分の七は男性。それを導いているのは、男女共学教育の内部で事実上の男女別々の領域にすすむような軌道がしかれているからだと指摘しました。
さらに、教授階層から女性教員が排除されているといいます。専門分野のピラミッドでは評価が一番高い領域では女性は少数派であり、正教授職という最高の職位階層に女性はほとんどいない。授業負担が重くプレステージの低い下層部分に、たくさんの女性がいる。「看過してよいのだろうか」と問う。高等教育で、女性たちが学問領域を選択するときに、女性と男性を異なる領域に追い込むような社会的圧力や文化的な要請という影響を受けている。制度として男女共学が実施されても現実は差別や偏見が横行しているという報告でした。状況はリアルであり、サマーズ学長発言に怒りが沸く女性たちの姿に重なるものでした。
アメリカは、女性の社会進出がすすみ、男女差別の課題でも人権の問題でも、「すすんだ国」と自負し、国連の場でも他国の人権問題を告発、制裁の先頭にたっています。「民主主義のモデル」をふりかざすことも少なくありません。
ところが、国連女性差別撤廃条約も子どもの権利条約も、ILO条約一〇〇号(同一価値の労働についての男女労働者にたいする同一報酬に関する条約)、一五六号(家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する条約)なども批准していません。女性差別撤廃条約は女性に対する差別だけを扱うものであり、合衆国憲法の平等規定に反するといいます。どちらかの性を「保護」するのは差別だという平等の論理は徹底しています。出産も健康状態を理由とする医療休暇であり、給与保障はしない。大学の女性に「仕事か家庭か」の選択を迫り、それで地位と評価を決めているのではないでしょうか。
男女平等とは、産む性である女性の生き方を社会的に保障するかどうか、利潤追求優先社会のありようとの攻防だとあらためて痛感します。
(広井暢子)