2004年2月6日(金)「しんぶん赤旗」
「益税」があるから免税制度の縮小は当然なのでしょうか。
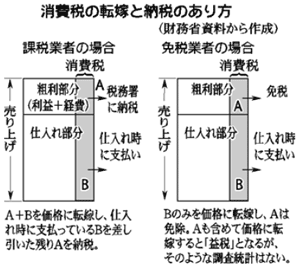 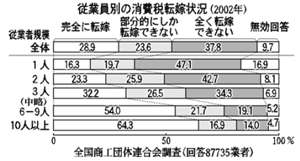
|
「免税業者が消費者の払った消費税をポケットにいれている。けしからん」と思っている人は案外多いかもしれません。しかし、これには「大いなる誤解」(商店街振興組合の幹部)があります。
消費税についてはこれまで、年間売上高が三千万円以下の業者は非課税業者(免税業者)としてきました。ところが、昨年の法改定で、免税とする売上高の上限を一千万円以下に引き下げることにしました。来年度の決算から課税を実施します。
改定の理由を小泉内閣は「消費者の支払った消費税相当額が国庫に入っていないのではないかとの疑念」を国民の間に呼んでいるから、信頼性を回復するためだといっています。
しかし、この理由は通用しません。
免税業者でも実は消費税を支払っています。商品を仕入れたり、材料を購入したりするときに取引先に払うというかたちでです。この分については商品価格に転嫁しなければなりません。消費税というのは、消費者に転嫁する制度だからです。(図参照)
「益税」とは、本来消費者に転嫁する分を超えて消費者から集めた場合に生じるものです。
しかし、現実には、小さな業者は、本来転嫁するはずの分も転嫁できないケースが大半で、「益税」どころではありません。
小規模業者を多数組織する全商連(全国商工団体連合会)の会員調査では、本来転嫁するべき消費税分をすべて転嫁できているのは29%にすぎません。61%の業者は完全な転嫁ができていません。つまり、六割以上の業者は「益税」どころか、消費税制度のせいで消費者からもらった分以上に納税しなければならないという「損税(そんぜい)」を迫られるのです。
背景には、大型店などとの競争や下請け構造のなかでの大手・親企業の優越的地位の乱用などがあります。
消費税は「消費者から支払ってもらっても、もらわなくても、課税業者は納税しなければならない」という税金です。
体力の強い大手スーパーは消費税分を価格引き下げで対応できても、小商店は消費税分を価格に上乗せするとますます価格差が広がるので、価格転嫁はなかなか難しいのです。
さらに、製造業などの下請け構造のなかでは、親企業が優越的地位を利用し「消費税分はまけといてくれ」などとして、実質的に消費税分を支払わない、という不公正取引が横行しています。
ところで、小泉内閣が消費税課税対象に広げた年商一千万円というのは、どのような業者でしょうか。
現行消費税の簡易課税制度で計算すると、年商一千万円の小売業なら粗利は二割(仕入れは八割)で二百万円、年商一千万円の製造業なら粗利は三割(同七割)で三百万円とされます。月額になおすとそれぞれ十七万円、二十五万円です。この額には経費などもふくまれており、家族を養うことも大変な額です。
消費税を価格に転嫁できずにやっと生活している零細業者にまで、小泉内閣は課税を広げようとしているのです。その目的は「益税」説を使って消費者の不満をそらし、さらなる消費税率アップを図ろうとするものとしかいいようがありません。
いまからでも、免税制度の縮小は撤回させなければなりません。