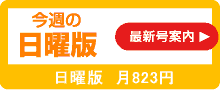2011年7月19日(火)「しんぶん赤旗」
アナログ停波
日本は国民合意なし
世界は段階的なのに
東日本大震災の被災3県を除く24日のアナログいっせい停波が、直前です。しかし、イギリス、韓国…世界では、各国が地域の実情を見ながら段階的な停波を進める、円滑な移行が潮流です。
1998年に世界に先駆けて地上デジタル放送(地デジ)を開始したイギリスは、段階的にデジタル移行をしています。
人口の最も少ないボーダー地域(2008年)を皮切りに、4年間で15地域を順次、移行し現在は8地域で移行が完了しています。人口の多いロンドン地域(12年)など、12年末には全土で移行終了の予定です。
移行開始前の06年には終了シミュレーション実験をコープランド地区で実施。高齢者や障害者などのデジタル弱者をどう支援するかを調査し、移行を円滑にする上での諸課題の発見と修正を何度も繰り返しています。
日本の方式と違い、標準画質方式でデジタル化を進めるイギリスでは、セットトップボックスを接続すれば手軽にデジタル放送を楽しめます。
「この円滑な移行の背景には、放送についてのイギリスのオープンな国民的な論議の伝統があります」というのは須藤春夫法政大学社会学部教授(マスメディア論)です。
厚い信頼
イギリスの公共放送BBCは、国王の特許状で事業内容が規定されますが、ほぼ10年ごとの更新時にBBCのあり方をどうするのか、国民的な議論が行われます。
06年に発効した現特許状は、03年から検討が始まりおよそ3年の時間を費やしました。政府は特許状見直しに関する文書を発表し、国民から意見を募集、また結果を公表します。寄せられた意見は1万件以上にのぼり、公開セミナー、公開ミーティングも開き、公開議論の参加者は3千人以上とみられています。
国民のBBCへの信頼も厚く、デジタル化などの技術の進歩によって「社会に貢献をもたらすべきだ」「技術についていくべきだ」などの意見が寄せられました。
そうした論議を通じて、政府はBBCの目的を「デジタル移行を先導する」「市民性と市民社会を支える」などと六つの柱を掲げました。
その目的について須藤教授は「国民は社会をつくる主人公として、あらゆる出来事とその背後にある真実を知ることが求められます。民主主義を育てること、そのためにBBCは政府の都合の悪いことも含めて知らせる監視役となることも目的にしている」と話します。
NHKは
日本のNHKにも5年ごとに更新する放送免許がありますが、放送の評価も目的の論議もなく事実上、自動的な更新です。
「国民的合意を図ったうえでデジタル化の導入を決めたBBCと、実際には政府や産業界の言うがままに国民的合意抜きでデジタル化に踏み切ったNHK。『皆様のNHK』というなら国民合意なしのこの方針に反対すべきだった」と話すのはメディア研究者の松田浩氏です。
「日本は法律で最初からアナログ停波のタイムリミットを決め、法律で縛ってデジタル化を強行するという、世界でも例を見ないほどの非民主的な方法をとったのです」と話します。(小林信治)