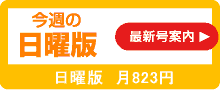2008年5月26日(月)「しんぶん赤旗」
四川大地震2週間
ボランティアら懸命に支援
明日へ心つなぐ
綿陽市の避難所
中国で大地震が発生して二十六日で二週間。四川省では、家族も生活の見通しも一瞬のうちに失った何十万、何百万の被災者が不安な日々を送り、当局やボランティアが必死の支援を続けています。震源地から東に百キロほど離れた綿陽の避難所を取材しました。(綿陽=山田俊英)
 (写真)九洲体育館脇の仮設の水道に集まる被災者ら=24日、中国四川省綿陽市(北條伸矢撮影) |
綿陽市の郊外にある九洲体育館。市内にいくつも設置されたなかで最大の避難所で、一万五千人が身を寄せています。臨時のトイレ、シャワー、診療所、学校が設けられ、市、ボランティア、被災者自身が運営しています。
自らも被災
「患者の大半は打撲などの外傷。入院が必要な人は病院に搬送した。ここには内科、外科、小児科、歯科、眼科、すべての診療科がそろっている。心のケアをする専門家はいま全員被災者のところに行って話を聞いている。鍼灸(しんきゅう)には毎日三百―四百人がくる」と、てきぱき語るのは避難所の漢方医療副主任、豊紀明医師(44)。綿陽市内の病院長です。
「自宅のドアは、ずれて開閉できない。パソコンも冷蔵庫もひっくり返った」
しかし、自宅はそのままにしてこの診療所脇のテントで寝泊まりしています。寝ていますかと聞くと、「毎日二―三時間寝ているから大丈夫」といいます。
三輪自動車に積んだ大鍋から被災者にいため物を配っていたのは近くに住む運転手、莆紹厳さん(47)。車は自分の商売用。この地域の障害者協会役員もしています。
「いつもいろいろな人たちに助けてもらっているから、今度は自分が助ける」と地域の三十世帯で金を出し合い、炊き出しで毎日千人分の昼食を持ってきます。
小中学校は体育館脇のテント。丈夫です。イタリア語が書いてあります。内務省の災害用テントでした。避難民の子を集めた臨時のクラス編成です。この日は土曜日で授業は休み。「心をつなごう。手をつなごう」と書いた子どもの描いた絵が張ってありました。
体育館の一角に厳重に見張りを立てた場所がありました。親を失った幼児の宿泊所です。「知らないおとなが近づくとおびえるので、こうしています」と避難所の広報担当、王暁剛さん。本来は中国共産党綿陽市委員会宣伝部の副部長です。
テント作りのシャワーは二十二日から使えるようになりました。給排水に限度があるので時間帯を決めて一人一回十五分の決まりです。「近くの企業や個人も会社や自宅に被災者を連れて行き、シャワーを提供している」と王さんはいいます。
不安乗せて
 (写真)九洲体育館前で移転先へのバスを待つ北川県の避難民=24日、綿陽市(山田俊英撮影) |
体育館前でバスに乗り込む人たちがいました。綿陽市北川県の住民です。県政府は県を丸ごと、五十キロ離れた安県に移すことを決断。既に県政府は安県に仮庁舎を開設しました。中国の県は、市の下にある農村部の行政単位を指します。
北川県では県全体が壊滅し、人口十六万人の約一割、一万五千人が死亡・行方不明です。山崩れのため水没した村もあり、苦渋の選択です。避難民を順次、安県内に設営したテントに移動させています。
「トウモロコシが育ち、豚肉の薫製もできたのに何も持ち出せなかった。政府から衣類や日用品はもらったが自分のものは何一つ持ち出せなかった。戻りたい。知らない土地で自分がどうなるのか、まったくわからない」と夏世春さん(43)は疲れきった表情で語ります。地震後、水が出て自宅と畑は水没しました。
移転先の住まいがどんなところか、畑があるのか、わかりません。不安な表情の人たちで満員のバスが出発しました。
中国四川省の大地震とミャンマーのサイクロンの被害にたいする救援募金の受け付け
日本共産党中央委員会は、中国四川省の大地震とミャンマーのサイクロンの被害にたいする救援募金を以下のように受け付けています。
郵便振替 00170―7―98422
口座名義 日本共産党中央委員会
通信欄に、募金先として「中国四川省大地震」、あるいは「ミャンマーのサイクロン」と明記してください(為替振替手数料が必要です)。